お茶の水女子大学の受験対策!難易度や偏差値、合格に向けての勉強法を解説
最終更新日:2023/03/31

こんにちは!四谷学院の奥野です。
お茶の水女子大学は、東京都文京区に本部を構える国立大学です。国立の女子大学は奈良女子大学と合わせて日本に2校しかなく、日本に数多くある女子大のなかでも、名門中の名門となっています。「お茶大」「お茶女」という略称で親しまれていますが、女子大の最高峰といわれるほど、難易度が高い大学としても知られており、憧れている受験生も多いでしょう。
しかし、お茶の水女子大学に入るためにどのような対策をすればいいのか分からず、悩んでいる受験生もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、お茶の水女子大学の求めている人材や難易度、受験方式や合格最低点、出願者などの各種データをご紹介します。また、記事の後半では、合格のための勉強方法も解説します。受験を予定している方は、ぜひ参考にしてみてください。
※本記事に記載されている情報は2023年3月22日現在のものです。最新の情報は大学公式ホームページにて必ずご確認ください。
目次
お茶の水女子大学で問われる能力と難易度

日本初の官立女子高等教育機関であるお茶の水女子大学は、2025年に創立150周年を迎える歴史ある名門大学。少人数制だからこそ実現する高度な教育は、文理融合のリベラルアーツを基礎としているのが特徴です。
そんなお茶大に入るためには、まず、お茶大がどのような人材(学生)を求めているのか、どれくらいの難易度なのかを把握しておきましょう。
お茶の水女子大学はどのような人材(学生)を求めているか?
お茶の水女子大学は、以下の標語を掲げ、多くの優れた女性たちを輩出してきた大学です。
お茶の水女子大学は、学ぶ意欲のあるすべての女性にとって、真摯な夢の実現の場として存在する。
引用元:お茶の水女子大学 大学憲章
その標語のとおり、お茶大の学士課程カリキュラム・ポリシーには、卒業論文や卒業研究の必要性とともに、創造力と実践性を備えた高度な専門的能力や発信・交渉能力、領域横断的な視野、変化に対応する判断力を身につけることが記載されています。
また、学士課程のアドミッション・ポリシーには、次のように書かれています。
お茶の水女子大学では、すべての女性が年齢・国籍などにかかわりなく自立した女性として、生涯にわたって多様に活躍できるキャリア形成の場を提供しています。知的好奇心と探究心を抱き、勉学意欲に富んだ学生の入学を期待しています。
引用:お茶の水女子大学HP
このように、お茶の水女子大学では主体的かつ積極的に学業に取り組んで、知識や広い視野を身につけられる人材を求めています。
お茶の水女子大学の難易度は?
Benesseの大学受験・進学情報「マナビジョン」のデータでは、お茶の水女子大学の入試の偏差値は61~72、共通テスト得点率は70~90%となっています。以下は、学部別の偏差値データです。
| 学部 | 偏差値 |
| 文教育 | 61~72 |
| 理 | 63~67 |
| 生活科 | 64~67 |
お茶の水女子大学の入試概要
受験生にとって最も重要なのが、入試概要。どの受験方式を選択するか、どの学部を志望するかによって、目指す学力ラインや対策が異なります。
ここでは、受験資格や試験科目と合格要件、出願者数や倍率のデータなど、お茶大の入試概要についてご説明します。
※本記事に記載のデータは、2022年3月22日現在のものです。
出願資格について
お茶の水女子大学の一般入試における出願資格は、以下の4つ。ただし下記に加えて、受験年度の共通テストで指定の教科、科目を受験する必要があります。
1.高等学校(中等教育学校を含む。)を卒業した者及び入学年の3月卒業見込みの者
2.通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び入学年の3月までに修了見込みの者
3.学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者及び入学年の3月31日までにこれに該当する見込みの者4.上記⑴⑵⑶に該当しない者について、大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で、18歳に達した者及び入学年の3月31日までに18歳に達する者。
試験科目や合格要件
ここでは、お茶の水女子大学の学部ごとの試験科目や配点をご紹介します。ここでは一般選抜前期日程の試験科目などについて解説します。なお、大学入学共通テストでは、指定された科目をもれなく受験するようにしてください。
文教育学部
文教育学部の試験科目や配点は、以下のとおり。ただし言語文化学科は数学を選択不可、芸術・表現行動学科は下記の試験科目に実技が追加されます。
| 教科 | 科目 | 出題範囲 | 配点 |
| 選択科目(どちらか1科目を選択) | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B | 200 ※芸術・表現行動学科 舞踏教育学 専修プログラムは100点 |
| 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B | ||
| 外国語 | 英語 | コミュニケーション英語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 200 ※芸術・表現行動学科 舞踏教育学 専修プログラムは100点 |
| 総合計 | 400 ※芸術・表現行動学科 舞踏教育学 専修プログラムは200点 |
||
理学部
理学部の試験科目は、以下のとおり。ただし、情報科学科は選択科目に数学が加わり、そこから2科目選択します。
また、物理学科は物理のみ選択可能、化学科は化学、生物学科は生物を選択したうえでさらに1科目選択します。学科によって試験科目や選択可能な科目が異なるので、注意してチェックしておきましょう。
| 教科 | 科目 | 出題範囲 | 配点 |
| 数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B | 100
※数学科はさらに専門科目で200点加わり、物理学科、情報科学科は200点の配点
|
| 理科(どれか1科目を選択) | 物理 | 物理基礎・物理 |
※物理学科・情報科学科は200点、化学科・生物学科は300点 |
| 生物 | 生物基礎・生物 | ||
| 化学 | 化学基礎・化学 | ||
| 外国語 | 英語 | コミュニケーション英語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 100
※物理学科は50点
|
| 総合計 | 500
※物理学科は450
|
||
生活科学部
生活科学部の試験科目は、学科ごとで異なります。受験する学科を決める参考にしてください。
<食物栄養学科、人間・環境科学科>
| 教科 | 科目 | 出題範囲 | 配点 |
| 数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B | 200 |
| 理科(どれか1科目を選択) | 物理 | 物理基礎・物理 | 100 |
| 生物 | 生物基礎・生物 | ||
| 化学 | 化学基礎・化学 | ||
| 外国語 | 英語 | コミュニケーション英語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 200 |
| 総合計 | 500 | ||
<人間生活学科、心理学科>
| 教科 | 科目 | 出題範囲 | 配点 |
| 選択科目(どちらか1科目選択) | 国語 | 国語総合、現代文B、古文B | 250 |
| 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B | ||
| 外国語 | 英語 | コミュニケーション英語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 250
|
| 総合計 | 500
|
||
出願者数や倍率は?
お茶の水女子大学の出願者数や合格者数は以下のとおりです。なお、ここで取り上げるのは2022年度(令和4年度)一般選抜前期日程の結果です。
| 学部 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 文教育 | 139 | 401 | 388 | 153 | 2.88 |
| 理 | 83 | 267 | 254 | 95 | 3.22 |
| 生活科 | 103 | 294 | 286 | 98 | 2.85 |
お茶の水女子大学に合格するための勉強方法
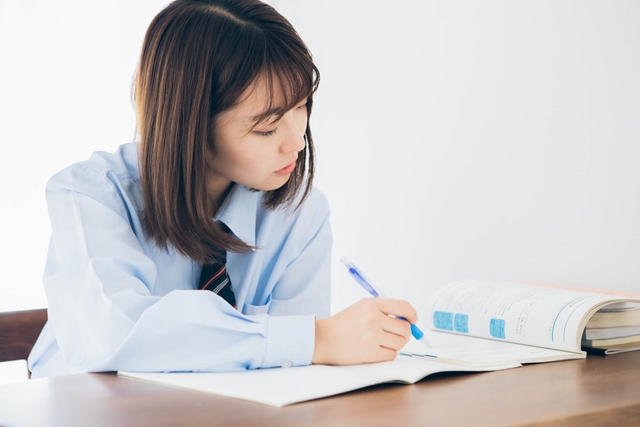
全国的に2校しかない国立の女子大であるお茶の水女子大学。ここまでアドミッション・ポリシーやデータなどを通じて紹介しましたが、「実際にどのような勉強をすれば合格できるのか?」を知りたいという方も多いでしょう。
ここでは、お茶大に合格するための勉強ポイントや受験期の過ごし方、予備校に通う際の注意点などを解説します。
お茶の水女子大学に入るには、何をすればいい?
お茶の水女子大学は女子大の最高峰といわれているだけあって、入試問題の難易度は高くなっています。さらに得点率も高いため、難易度の高い問題であっても高得点を獲得しなければなりません。
記述式や論述など、自分の考えを書いたり解にいたる過程を分かりやすく書いたりする問題が多く出題されるため、問題演習などで知識の活用・応用を訓練しておく必要があります。
典型的な問題もある一方、独特な問題も出題される傾向にあるので、過去問は繰り返し解いておくのがおすすめです。
受験期の過ごし方
高校3年生の1年間は、受験において重要な期間です。この時期の過ごし方によっては、大きく成績を伸ばすことも可能です。しかし、「どうすればいいか分からない」「何をポイントにスケジュールを立てればいいか分からない」という方も多いでしょう。
そこでここでは、季節ごとにおすすめの過ごし方をご紹介します。
- 春(4〜6月):基本を徹底して行いましょう。教科書や問題集、青チャートなどを利用して、苦手分野のあぶり出しと基礎学力の向上を図ります。
- 夏(7〜9月):長期休みでまとまった時間がとれる夏は、苦手分野を克服するのに最適な期間。春に見つけた苦手分野を集中的に潰して、基礎の総復習をしましょう。夏休み前に日々の学習計画を立てておくのがおすすめです。
- 秋(10〜12月):基礎固めが完璧にできたら、問題演習を行う期間。共通テストの予想問題集や模試などを利用して、これまでに身に付けた知識のアウトプットの訓練をしましょう。
- 冬(1月〜):共通テスト対策と同時並行して、個別学力検査の対策を行いましょう。問題の傾向などを把握して、効率良く対策することが大切です。過去問を解いて終わり、ではなく、解答や解説を見て復習が必要な箇所がないか確認しましょう。
勉強ポイント
各科目の勉強ポイントは、以下のとおり。
- 英語:お茶大の英語は、全問記述式。長文問題3つと英作文問題1つの4つの大問で構成されていることがほとんどなので、文法をしっかりと学習しておくことが大切です。長文問題の難易度は高めなので、速読力と正確性を身に付けることもポイントです。
- 国語:現代文、古文、漢文が、それぞれ1つずつの計3つの大問で構成されています。古文、漢文の難易度はそれほど高くありませんが、用語などの知識が必要。現代文は評論であることが多く、意見論述があるのが特徴です。自分の考えを分かりやすく書けるように、練習しておきましょう。
- 数学:共通問題の数学では、数学ⅠA、ⅡBの範囲から出題されることがほとんど。問題のレベルは標準程度ですが、だからこそ1つのミスが合否に大きく響きます。取りこぼしのないように点数をとれるよう、確実性を上げる勉強をしておきましょう。専門科目の数学は、数学Ⅲからの出題がほとんど。難易度もかなり上がるので、過去問演習を繰り返しましょう。
- 物理:近年は力学からの出題が多くみられ、それ以外は電磁気学、波動、熱力学の3分野からまんべんなく出題されます。記述式なので、答えにいたる過程も重視されるのが特徴。近似式も頻出しているので、問題演習や過去問演習で対策しておきましょう。
- 化学:計算量が多いのが特徴。ほかの大学入試ではあまり見られない問題もあるので、基本的な知識はもちろん、応用できる力を身につけておくことが重要です。解答は記述式で、論述問題もあります。
- 生物:実験考察問題が中心。問題の情報量が多いので、いかに短い時間で与えられた情報を整理できるかが重要になります。こちらも難易度は高く、ほかの大学入試ではあまり見られない問題もあるので、過去問演習などで対策をしましょう。
予備校で勉強する場合
「受験期の過ごし方」の項で、高校3年生の1年間の過ごし方によって成績の伸びが大きく異なる、と述べましたが、「予備校に通っているから大丈夫」と思った方もいるのではないでしょうか?
しかし、予備校に通っているからといって、効率良く成績を伸ばせるわけではありません。
特に予備校で集団授業だけを受けている学生は要注意。授業を受けているだけで「理解したつもり」になっている可能性が高いからです。
実際、集団授業は講師から生徒への一方通行なので、知識のインプットはできても、アウトプットは難しいのです。
お茶大の入試では「知識のアウトプット力」が重要視されるので、予備校に通うだけではなく、自分でアウトプットの訓練をする必要があります。
予備校の注意点・落とし穴については以下の記事もぜひご覧ください。
四谷学院のカリキュラムのご案内
お茶大に必要な「知識のアウトプット力」を養うために有効なのが、科目別能力別授業と55段階個別指導の2つを組み合わせた四谷学院独自の「ダブル教育システム」です。
ここでは「ダブル教育システム」の柱である科目別能力別授業と55段階個別指導についてご説明します。
科目別能力別授業
一般的な予備校でありがちなのが、模試などの総合得点でクラス分けをしているケース。
対して四谷学院では、科目と能力の2つでクラスを分けているのが特徴です。これにより自分の学習レベルにあった授業を受けられます。そのため、「苦手分野では付いていけない」「得意分野では暇をもてあます」といった心配がありません。
自分の学習レベルに合った授業を受けると、より早く深い理解が可能になり、自分のレベルを客観視することも可能。目標となるレベルもはっきりするので、効率良く学習できます。
科目別能力別授業の詳細はこちら!
55段階個別指導
上の項でも述べたように、集団授業は講師から生徒への一方通行。これは科目別能力別授業でも変わりありません。
そこで四谷学院では、生徒の理解度に合わせた演習問題を行う「55段階個別指導」を導入しています。マンツーマンなので、講師が苦手分野やお茶大合格に足りない力を見つけ出して、生徒に合った演習ができるのがポイントです。
演習で知識のアウトプットを繰り返すことで、確実な知識の定着と受験に必要な実践力を身につけられます。
55段階個別指導の詳細はこちら!
まとめ
【お茶大の入試概要】
- 知的好奇心と探究心があり、勉学意欲に富んだ人材を求めている
- 共通テストのスコアと個別学力検査、学科によっては実技試験が課せられる
- 学部によって多少異なるが、難易度は難しめ
【お茶大の入試データまとめ】
- 一般選抜前期日程における倍率は、おおむね3倍(令和4年度データ)。
【勉強方法まとめ】
- 記述や論述対策が必須
- 難易度の高い問題や珍しい問題が出題されるので、知識の応用力を身につけておく
名門中の名門であるお茶の水女子大学は、難易度がとても高い大学です。倍率こそ高くありませんが、ハイレベルな戦いが予想されます。
お茶大に合格したい方は、ぜひ四谷学院への入学をご検討ください。効率的な教育効果を実感できる四谷学院の「ダブル教育」システムで、効率良く合格を目指しましょう。
※本記事でご紹介した情報は2023年3月22日現在のものです。最新の情報は大学公式ホームページにて必ずご確認ください。
失敗しない予備校選びは説明会参加が重要!
予備校選びは合否に直結すると言っても過言ではありません。ネットで口コミを調べたり予備校のパンフレットを見たりするだけでは、得られる情報に限界があります。自分に合った予備校を選ぶには、説明会に参加して、直接あなたの目で確かめるのが一番!
以下の記事では、予備校の入学説明会について詳しく解説しています。ぜひチェックして、予備校の説明会に参加するときに感じがちな疑問や不安を解消してください。

大学受験合格ブログ編集部
このブログは、大学受験予備校の四谷学院の「受験コンサルタントチーム」「講師チーム」「受験指導部チーム」が担当しています。 大学受験合格ブログでは、勉強方法や学習アドバイスから、保護者の方に向けた「受験生サポート」の仕方まで幅広く、皆様のお悩みに役立つ情報を発信しています。
こんな記事も読まれています
前の記事 » 受験勉強は高3の6月からでもまだ間に合う!入試までにやるべき学習とは?
次の記事 » 予備校の夏期講習だけでも効果はある?受験生必見のメリットを解説
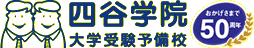






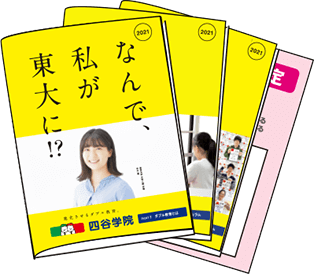


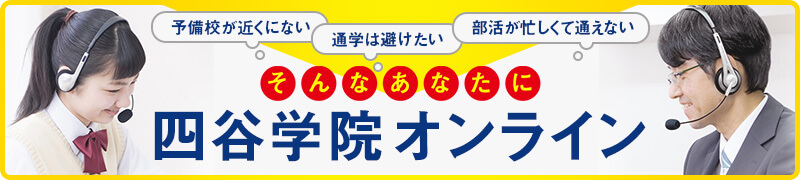
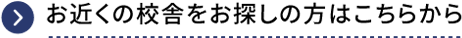
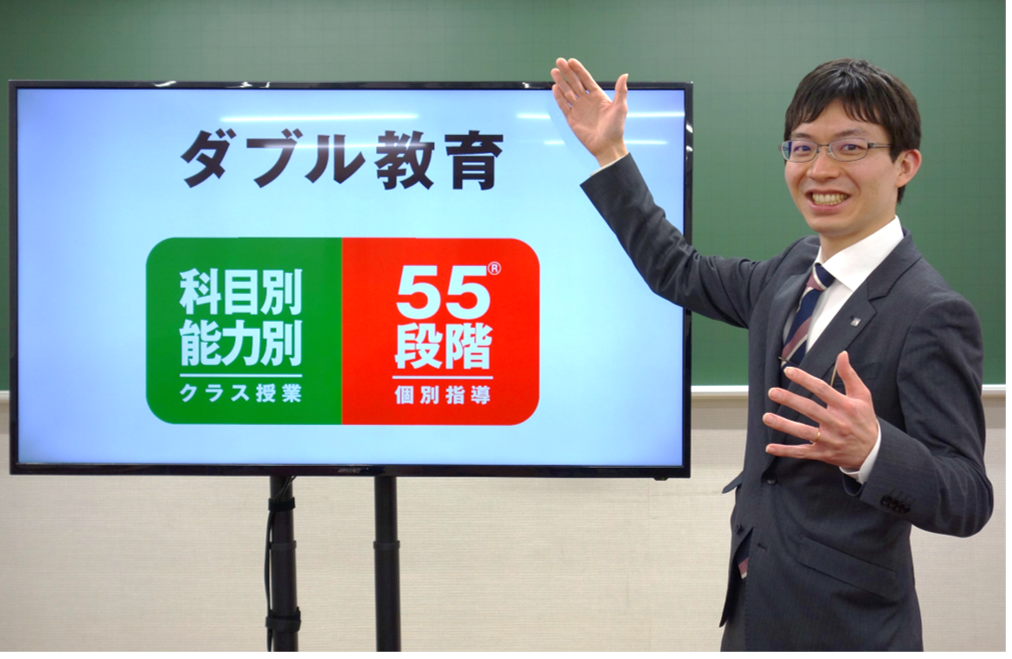
 ▶受験指導部チーム
▶受験指導部チーム