
こんにちは!四谷学院の奥野です。
成蹊大学(せいけいだいがく)は、東京都武蔵野市にキャンパスを展開する成蹊学園のなかに含まれる私立大学。
教育者・中村春二が1906年に開いた学生塾「成蹊園」を起源とし、1949年に創設されました。正門前から学園内に広がるケヤキ並木が有名で、「新東京百景」や「武蔵野市天然記念物」などに指定されています。
この記事では、成蹊大学の入試の特徴や難易度、倍率、成蹊大学に合格するための効率的な勉強方法を紹介します。
成蹊大学の受験を考えている方、勉強しているのに成績が伸び悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
※本記事に記載されている情報は2024年3月6日現在のものです。最新の情報は大学公式サイトにて必ずご確認ください。
目次
成蹊大学の概要

成蹊大学は東京都武蔵野市吉祥寺に位置し、経済学部・経営学部・法学部・文学部・理工学部の5つの学部で構成されています。
1つのキャンパスに文系・理系の学部・学科が収まっており、異なる学部の生徒とも交流できるのが特徴です。さらに、スポーツ施設や学生会館などさまざまな施設がそろっているため、学業と課外活動とを両立しやすい環境になっています。
設立年:1949年
学生数:7,633名(2023年5月1日時点)
所在地:〒180-8633
東京都武蔵野市吉祥寺北町3-3-1
公式サイト:成蹊大学
SNS:
Instagram:seikei_official
X(旧Twitter):@seikei_zelkova
成蹊大学の学部別偏差値と難易度(レベル)
Benesse「マナビジョン」のデータでは、2024年3月現在の成蹊大学の偏差値は52~65、大学入学共通テストの得点率は65~79%となっています。なお、学部ごとの偏差値は以下のとおりです。
| 学部 | 偏差値の範囲 |
| 文学部 | 56~65 |
| 法学部 | 57~63 |
| 経済学部 | 61~65 |
| 経営学部 | 62~65 |
| 理工学部 | 52~56 |
参照:成蹊大学/偏差値・入試難易度【2023年度入試・2022年進研模試情報最新】|マナビジョン|Benesseの大学受験・進学情報
成蹊大学は、関東の大学群である「成成明学獨國武」に属している大学です。偏差値を見ると、この大学群の上位に位置し、難関私立大学の大学群である「GMARCH」よりやや下回ることから、準難関大学といえるでしょう。
成蹊大学と近い偏差値・難易度(レベル)の大学
ここでは、成蹊大学と近い偏差値・難易度(レベル)の大学をいくつか紹介します。
■偏差値の近い大学「文学部」
愛知大学 文学部(偏差値51~63)
青山学院大学 文学部(偏差値65~73)
追手門学院大学 文学部(50~58)
■偏差値の近い大学「法学部」
関西学院大学 法学部(63~71)
京都女子大学 法学部(56~62)
甲南大学 法学部(54~59)
■偏差値の近い大学「経営学部」
駒澤大学 経営学部(57~63)
成蹊大学 経営学部(62~65)
専修大学 経営学部(54~62)
■偏差値の近い大学「経済学部」
國學院大學 経済学部(62~64)
駒澤大学 経済学部(54~63)
上智大学 経済学部(61~65)
■偏差値の近い大学「理工学部」
関西大学 システム理工学部(偏差値55~61)
関東学院大学 理工学部(46~52)
摂南大学 理工学部(偏差値48~55)
成蹊大学入試の特徴
成蹊大学ではさまざまな選抜方式が導入されており、一般選抜や総合型選抜(AOマルデス入試)、学校推薦型選抜などがあります。
そのなかでも、多くの受験生がチャレンジする一般選抜には、次のような6種類の入試方法があります。
3教科型学部個別入試(A方式)
大学独自の試験です。学部ごとの日程で実施される3教科を受験する方式で、3教科の合計点で判定されます。試験日を変えれば、複数の学部に出願が可能です。
2教科型全学部統一入試(E方式)
全学部で同じ日に実施される独自試験で、2教科を受験する方式です。成蹊大学以外に、全国5会場(仙台、さいたま、横浜、静岡、福岡)でも受験できます。
2教科型グローバル教育プログラム統一入試(G方式)
現代経済学科・総合経営学科・法律学科・政治学科・英語英米文学科・国際文化学科で実施される方式です。
独自試験の得点に、提出書類の得点(段階評価)と英語外部検定試験のスコア(換算得点)を加えて合否判定を行います。
共通テスト利用3教科型入試(C方式)
独自試験は実施せず、大学入学共通テストの3教科のみで合否判定を行う方式です。
共通テスト利用4教科6科目型奨学金付入試(S方式)
理工学部のみで実施される方式です。すべての専攻に併願でき、合否は大学入学共通テストの6科目の合計点で判定されます。
この方式では、入学者全員が「成蹊大学入学試験特別奨学金」の給付対象になります。
共通テスト・独自併用 5科目型国公立併願アシスト入試(P方式)
経済学部・経営学部・法学部・文学部で実施される方式です。独自試験1科目と、大学入学共通テスト5科目との合計で合否判定を行います。
前期日程の合格発表後に入学手続きの締め切りが設定されているため、国公立大学との併願がしやすくなっています。
成蹊大学の入試科目別の出題範囲とその対策
成蹊大学の入試対策をするうえでは、試験問題の特徴や傾向をつかんでおくことが大切です。成蹊大学では数多くの選抜方式を導入していますが、独自試験としては2教科型と3教科型に大きく分けられます。
そのため、ここでは3教科型学部個別入試(A方式)を取り上げて、成蹊大学の試験問題の特徴を一部紹介します。
なお、受験する教科は学部・学科によって異なりますが、多くの学科で受験科目とされている英語・国語・数学を紹介しています。
英語の対策と勉強法
成蹊大学の英語は、標準的な難易度といえるでしょう。試験時間は60分の学部が大半ですが、経済学部のみ国語と合わせて90分枠になっています。
学部によって問題が異なりますが、いずれも長文読解は出題される傾向にあります。内容の把握が必要になるため、段落ごとに要点をつかみながら文章全体を把握する読み方(パラグラフリーディング)の練習をするのがおすすめです。
基礎的な文法や語彙をしっかりと学習したうえで、長文対策に取り組みましょう。
国語の対策と勉強法
成蹊大学の国語は、標準~やや難しいレベルの難易度といえます。多くの学部では試験時間60分となっていますが、経済学部のみ英語と合わせて90分枠です。
試験範囲は文学部のみ国語総合(近代以降の文章)、現代文B、古典Bとなっていますが、その他の学部では国語総合、現代文Bとなっています。なお、理工学部では国語の試験はありません。
どの学部でも、おもに評論文が出題される傾向にあります。
内容を読み取る形式の設問が多いため、いかに段落の要旨や筆者の主張を正確に読み取れるかがカギとなるでしょう。
漢字の書き取りや四字熟語、慣用句などに関する知識問題もよく出されるため、対策しておきましょう。
文学部も現代文では評論文がメインですが、古文では現代語訳や文法、漢文では漢字の読みや文法など幅広く出題されます。
数学の対策と勉強法
数学は経済学部経済数理学科と理工学部では必須科目、経済学部現代経済学科・法学部・経営学部では選択科目となっています。
試験時間は理工学部のみ90分、その他の学部は60分です。難易度は標準レベルといえるでしょう。
経済学部・経営学部では数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学Bが、法学部では数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Aが出題範囲となっています。
出題範囲からまんべんなく出されますが、「図形と方程式」や「確率」がやや頻出傾向にあります。公式をしっかりと暗記し、計算力が身に付けられるように演習を重ねることが大切です。
一方、理工学部では出題範囲に数学Ⅲが含まれており、数学Ⅲを中心に幅広く出題されます。数学Ⅲをおろそかにせず、集中的に学習しましょう。
成蹊大学の入試概要
ここからは、成蹊大学の入試概要について解説します。
出願資格について
成蹊大学の出願資格は選抜方式によって異なるため、ここでは一般選抜での出願資格を紹介します。
一般選抜の出願資格は次のとおりです。
- 高等学校または中等教育学校を卒業した者、および入学年の3月卒業見込みの者
高等専門学校の3年次を修了した者、および入学年の3月修了見込みの者 - 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により、
これに相当する学校教育を修了した者を含む)、および入学年の3月修了見込みの者 - 学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、および入学年の3月31日までにこれに該当する見込みの者
入試日と出願の受付期限
入試日や出願期間についても選抜方式によって異なるため、ここでは一般選抜を取り上げて紹介します。
一般選抜の出願受付は、2024年1月5日(金)からスタートします。締め切りと試験日は、一般選抜のなかでも入試の種類や学部などによって異なるため「2024年度入学試験要項」でご確認ください。
なお、大学入学共通テストの出願期間は2023年9月25日(月)~10月5日(木)で、試験日は2024年1月13日(土)と1月14日(日)となっています。
入試科目や配点
続いて、成蹊大学の学部ごとの試験科目や配点について解説します。
ここでは、一般選抜の3教科型学部個別入試(A方式)の試験科目に絞って取り上げます。3教科型学部個別入試(A方式)では科目ごとの基準点はなく、受験する3教科の合計点数で合否判定されます。
なお、以下のデータはすべて2023/11/2現在のものです。
<経済学部>
| 学科 | 教科 | 出題科目 | 配点 |
| 経済数理学科 | 外国語 | 「英語(コミュニケーション英語Ⅰ)、(コミュニケーション英語Ⅱ)、(コミュニケーション英語Ⅲ)、(英語表現Ⅰ)、(英語表現Ⅱ)」 | 200 (外国語100、国語100) |
| 国語 | 「国語総合(近代以降の文章)」「現代文B」 | ||
| 数学 | 「数学Ⅰ」「数学Ⅱ」「数学A」「数学B(数列、ベクトル)」 | 200 | |
| 現代経済学科 | 外国語 | 「英語(コミュニケーション英語Ⅰ)、(コミュニケーション英語Ⅱ)、(コミュニケーション英語Ⅲ)、(英語表現Ⅰ)、(英語表現Ⅱ)」 | 200 (外国語100、国語100) |
| 国語 | 「国語総合(近代以降の文章)」「現代文B」 | ||
| 地理歴史 公民 数学 | 「日本史B」「世界史B」「政治・経済」、「数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル)」から1科目選択 | 100 |
<経営学部>
| 学科 | 教科 | 出題科目 | 配点 |
| 総合経営学科 | 国語 | 「国語総合(近代以降の文章)」「現代文B」 | 100 |
| 地理歴史 数学 | 「日本史B」「世界史B」「数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル)」から1科目選択 | 100 | |
| 外国語 | 「英語(コミュニケーション英語Ⅰ)、(コミュニケーション英語Ⅱ)、(コミュニケーション英語Ⅲ)、(英語表現Ⅰ)、(英語表現Ⅱ)」 | 150 |
<法学部>
| 学科 | 教科 | 出題科目 | 配点 |
| 法律学科 政治学科 | 国語 | 「国語総合(近代以降の文章)」「現代文B」 | 100 |
| 地理歴史 公民 数学 | 「日本史B」「世界史B」「政治・経済」「数学Ⅰ(「データの分析」を除く)、数学Ⅱ、数学A」から1科目選択 | 100 | |
| 外国語 | 「英語(コミュニケーション英語Ⅰ)、(コミュニケーション英語Ⅱ)、(コミュニケーション英語Ⅲ)、(英語表現Ⅰ)、(英語表現Ⅱ)」 | 120 |
<文学部>
文学部は学科により、外国語の配点が異なります。
| 学科 | 教科 | 出題科目 | 配点 |
| 英語英米文学科 日本文学科 国際文化学科 現代社会学科 | 国語 | 「国語総合」「現代文B」「古典B」 | 150 |
| 地理歴史 | 「日本史B」「世界史B」から1科目選択 | 100 | |
| 外国語 | 「英語(コミュニケーション英語Ⅰ)、(コミュニケーション英語Ⅱ)、(コミュニケーション英語Ⅲ)、(英語表現Ⅰ)、(英語表現Ⅱ)」 | 英語英米文学科:200 日本文学科:100 国際文化学科、現代社会学科:150 |
<理工学部>
| 学科 | 教科 | 出題科目 | 配点 |
| 理工学科(データ数理専攻・コンピュータ科学専攻・機械システム専攻・電気電子専攻・応用化学専攻) | 数学 | 「数学Ⅰ」「数学Ⅱ」「数学Ⅲ」「数学A」「数学B(数列、ベクトル)」 | 120 |
| 理科 | 「物理(物理基礎、物理)」「化学(化学基礎、化学)」「生物(生物基礎、生物)」から1科目選択 | 120 | |
| 外国語 | 「英語(コミュニケーション英語Ⅰ)、(コミュニケーション英語Ⅱ)、(コミュニケーション英語Ⅲ)、(英語表現Ⅰ)、(英語表現Ⅱ)」 | 120 |
参照:成蹊大学 2024年度入学試験要項
出願者数や合格者数のデータ
成蹊大学の出願者数や合格者数は選抜方式によって異なるため、ここでは一般選抜3教科型学部個別入試(A方式)について紹介します。各学部の2023年のデータは以下のとおりです。
| 学部・学科 | 実質倍率 | 受験者数 | 合格者数 | |
| 経済学部 | 経済数理学科 | 6.0 | 353 | 59 |
| 現代経済学科 | 7.8 | 1,063 | 136 | |
| 経営学部 | 総合経営学科 | 4.3 | 1,782 | 416 |
| 法学部
| 法律学科 | 4.0 | 1,035 | 258 |
| 政治学科 | 3.3 | 550 | 165 | |
| 文学部
| 英語英米文学科 | 2.5 | 257 | 101 |
| 日本文学科 | 3.7 | 303 | 81 | |
| 国際文化学科 | 2.1 | 225 | 105 | |
| 現代社会学科 | 3.2 | 338 | 105 | |
| 理工学部 | データ数理専攻 | 3.4 | 326 | 97 |
| コンピュータ科学専攻 | 6.5 | 387 | 60 | |
| 機械システム専攻 | 5.4 | 399 | 74 | |
| 電気電子専攻 | 3.9 | 291 | 74 | |
| 応用化学専攻 | 5.0 | 322 | 64 | |
参照:成蹊大学 入試結果
成蹊大学の受験料と学費目安
ここでは、最も受験者数の多い一般選抜の受験料を紹介します。
受験料は、以下のように選抜方式によって異なります。
| 選抜方式 | 金額 |
| 3教科型学部個別入試(A方式) | 1学部・1専攻あたり35,000円 |
| 2教科型全学部統一入試(E方式) | 1学部あたり35,000円 |
| 2教科型グローバル教育プログラム統一入試(G方式) | |
| 共通テスト利用3教科型入試(C方式) | 1学部・1専攻あたり15,000円 |
| 共通テスト利用4教科6科目型奨学金付入試(S方式) | |
| 共通テスト・独自併用 5科目型国公立併願アシスト入試(P方式) | 1学部あたり25,000円 |
併願する場合は、2つ目以降の受験料が1つごとに10,000円割引される併願割引制度を利用するとよいでしょう。
また授業料は学部によって異なり、経済学部・経営学部・法学部・⽂学部は年間で825,000円、理工学部は1,060,000円となっています。
成蹊大学卒業後の進路
2022年度における成蹊大学の卒業生の就職率は95.1%で、サービス業やIT業、製造業、金融業などへの就職率が高くなっています。
おもな就職先に、三菱UFJ銀行や三井住友信託銀行、清水建設、日本航空、西武鉄道、厚生労働省などがあります。
成蹊大学が気になった人はオープンキャンパスや進学相談会へ
成蹊大学への進学を検討している方は、オープンキャンパスや進学相談会への参加をおすすめします。
これらは、大学の雰囲気や学生生活などを把握できる貴重な機会です。それに加えて、入学に関する情報についても詳しく知ることができます。
進学に対する疑問点や不安点がある場合は、教員や在校生に質問できるため、積極的に参加してみるとよいでしょう。
成蹊大学に合格するための勉強方法
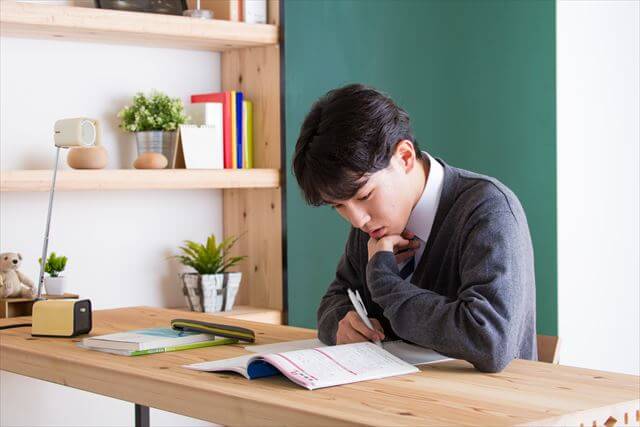
ここからは、成蹊大学に合格するための学習方法を紹介します。
成蹊大学に入るには、何をすればいい?
成蹊大学の選抜方式は多様で、一般選抜だけでも独自試験として3教科型と2教科型があるほか、大学入学共通テストのみを利用する方式や大学入学共通テストと独自試験を組み合わせた方式があります。
受験生は自分の得意科目を考慮して適した方式を選択できますが、成蹊大学は人気が高いため、競争率が高くなりやすいでしょう。
ちょっとしたミスが合否を分けることになりかねないため、志望学部・学科の学習内容を把握し、失点を最小限に抑えることが大切です。
受験期の過ごし方と勉強のコツ
高校3年生の受験期をどのように過ごすかで、合格の確率は変動します。手当たり次第に勉強するのではなく、1年を通じて受験勉強の長期的なスケジュールを立てましょう。
- 春(4~5月):まずは基礎を徹底して身に付けましょう。基礎を押さえるためには、教科書を丁寧に学習し、単語や用語といった暗記ものにできるだけ早く取りかかるのが重要です。また、この時期に苦手分野の洗い出しも行いましょう。
- 夏(6~8月):夏は苦手分野を克服する時期と考え、まとまった学習に取り組んで成績アップを目指しましょう。夏休みには「一日に問題集を10ページ進める」など、短いスパンで達成できるスケジュールで進めるのも効果的です。
- 秋(9~11月):夏休み後は、大学入学共通テストの対策を始める時期です。個別学力検査の対策もかねて、基礎固めをしつつ応用力を磨きます。
- 冬(12月~):入試直前は過去問を集中的に学習し、演習を積みます。ミスがないように集中しつつ、時間配分にも注意して問題を解くようにし、最後の仕上げをしましょう。
成蹊大学を目指すなら予備校を使って入試対策をしよう
独学で受験対策を進める場合は、継続する意志と情報収集力が必要です。そのため、成蹊大学への合格を本気で目指すなら、予備校へ通うのがおすすめだといえます。
ただし、 予備校に通う場合には、いくつか注意が必要です。
多くの予備校では集団授業を行っており、多数の生徒が一度に同じ授業を受けています。しかし、ただ授業を受けるだけでは知識が定着しづらく、苦手な分野が取り残される可能性もあるでしょう。そのため、自分から積極的に質問し、学習効果を高めることが大切です。
四谷学院のカリキュラムのご案内
予備校の授業に起きやすい欠点をカバーしてくれるのが、四谷学院の「ダブル教育」です。ダブル教育の2つのポイントをチェックしてみましょう。
科目別能力別授業
多くの予備校では、志望校やテストの総合得点でクラス分けをします。そのため、苦手科目の授業についていけない、得意科目の授業が物足りないなど、科目ごとのレベルの不一致が起こることがあります。
四谷学院の科目別能力別授業は、科目と能力の2つでクラス分けするのが特徴です。科目ごとに自分のレベルに合った授業を受けられるので、無理なく理解が進み、効率的に成績向上を目指せます。
55段階個別指導
55段階個別指導では、科目別能力別授業で得た理解力を、解答力へとつなげていきます。
過去の入試問題を徹底的に分析して作成した55テストを使って、生徒の理解に穴があるところ、考え方が不完全なところ、表現が不適切なところをチェック。
解答力が身に付いているかを確認しながら級を進め、中学レベルから東大レベルまでを、55段階のスモールステップで無駄なく学べるように体系化して指導しています。
成蹊大学に合格するには丁寧に解く力が重要!
【成蹊大学の入試概要】
- 緑の豊かな環境で、文系理系が同じキャンパスで学べる。
- 多彩な選抜方式で、自分に合った選抜方式が選びやすい。
- 難易度は標準的だが試験時間にあまり余裕がないため、解くスピードが必要。
【成蹊大学の入試データまとめ】
- 2023年度のデータを見ると、実質倍率は一般選抜全体で2.1~6.5倍。選抜方式や学部・学科により大きな差がある。
【勉強方法まとめ】
- 英語や数学など、解き方の理解が必要な問題も多い。教科書や用語集を丁寧に学習して基礎固めが必要。
- 試験時間60分の教科が多いため、時間配分の練習が必要。
成蹊大学の入試問題の難易度はそれほど高くありませんが、人気が高いためハイレベルな戦いになりやすい大学。基礎を徹底したうえで、いかにミスを少なくして問題を解くかが重要になってきます。そこでおすすめなのが、四谷学院の「ダブル教育」。
自分の学習レベルにあった授業で、効率的な成績向上が望めます。気になる方はぜひお気軽にお問い合わせください。
※本記事でご紹介した情報は2024年3月6日現在のものです。最新の情報は大学公式サイトにて必ずご確認ください。
失敗しない予備校選びは相談会・説明会参加が重要!
予備校選びは、大学受験の合否に大きな影響を与えるといっても過言ではありません。インターネットで確認できる情報だけでは限りがあるため、実際に説明会に参加して、自分に合った予備校を選びましょう。
以下の記事では、予備校の説明会について詳しく解説しています。説明会に参加する際の疑問や不安を解消するためにも、ぜひご一読ください。



