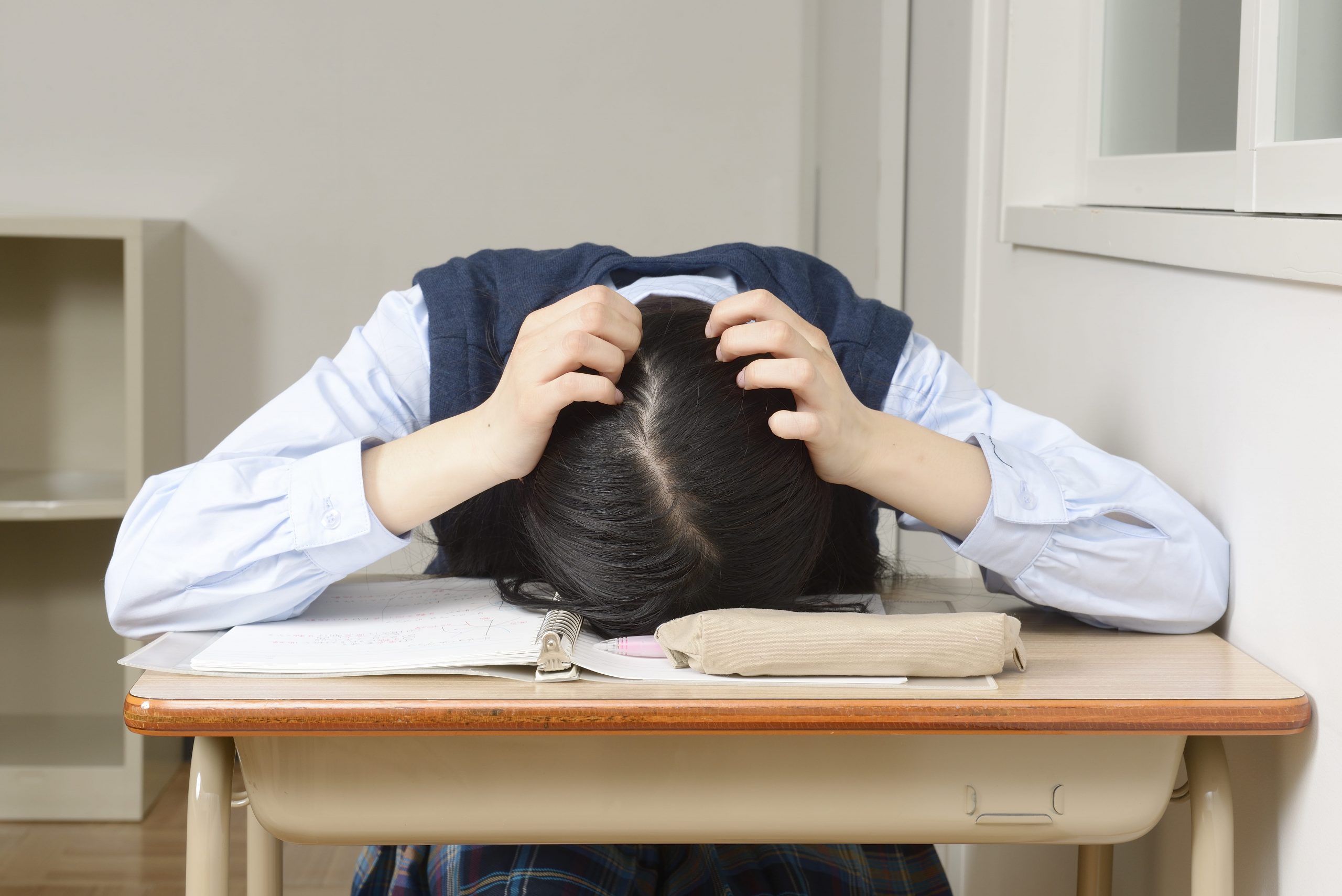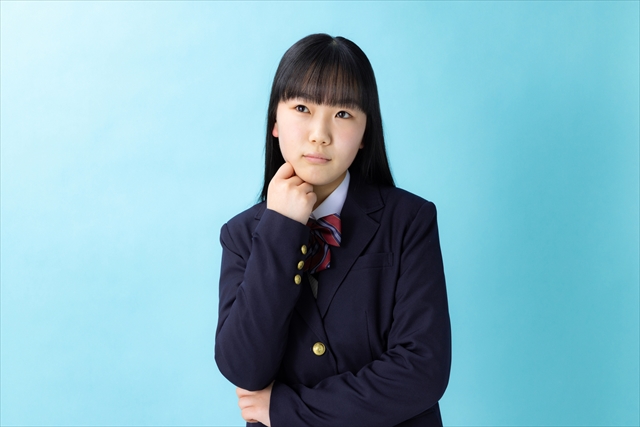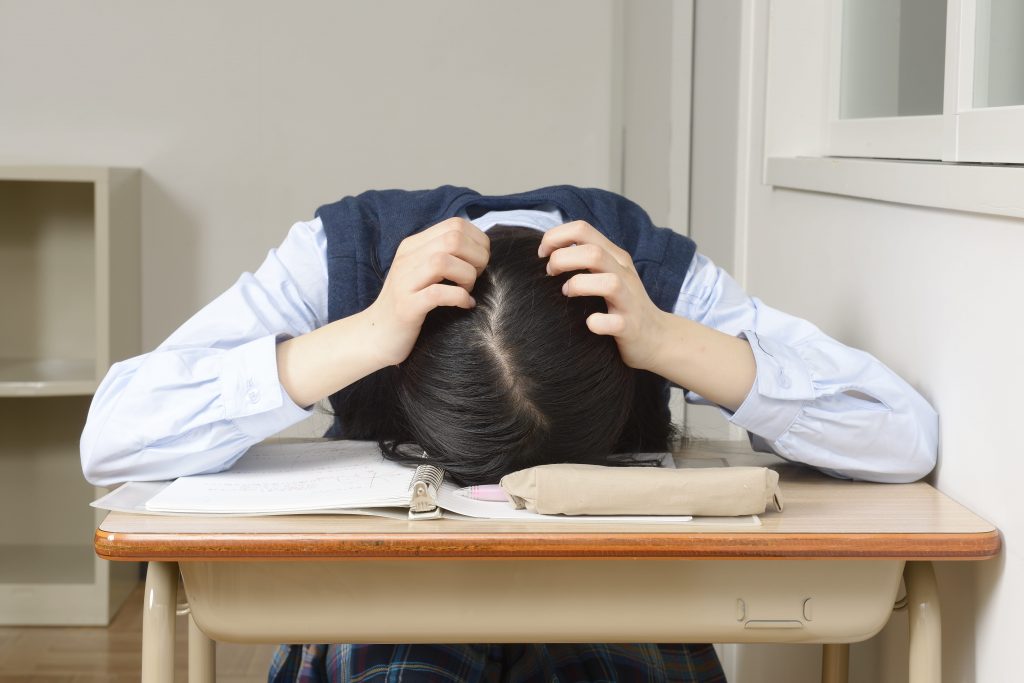
こんにちは、四谷学院の受験コンサルタント、田中です。
多くの高校生は、進路選択の最初の分岐点として、高校1年生から2年生にかけて、文系コース・理系コース、どちらのコースに進むかの選択を迫られます。
今回は、「文理選択をする上でのポイント」と「文転・理転する際の注意点」を確認していきます。
目次
文理選択のタイミング
ほとんどの高校では、高校1年生の冬に文理選択の調査を行い、2年生の授業から文系/理系のクラスにわかれます。理科の履修範囲や、数学の授業進度などが大きく異なります。
現役で合格する先輩たちの多くは、高校の勉強をおろそかにせず、「基礎固めの機会」として活用し、受験勉強と学校の勉強を両立させています。
大学受験でまったく使わない科目を多く履修するコースに進んでしまうと、学習量や負担が増えてしまいます。文系理系の違いを甘くとらえ、よく考えずに選択して後悔する先輩も少なくありません。大学受験で必要な科目が中心となるようなカリキュラムを選択したいところです。
文理選択の時期は早まっている?
以前は、高校1年生の12月から1月に文理選択の説明、決定がありました。しかし、最近では、文理選択を考え始める時期が早まっています。高校1年生の夏休みを使って大学のオープンキャンパスに参加できるよう、1学期には文理選択についての説明をされる高校も多く、文理選択とともに進学先も検討できる時間が増えています。そして、1月頃に文系・理系いずれのコースに進むのかを決定します。
<h3>文転や理転は可能なのか</h3>
文転や理転をする上で、一番ネックになるのは科目負担。高校で文理選択を間違っていると、
「数Ⅲを学校で教えてもらえなかった!」
「学校の定期試験のためだけに受験で必要ない専門理科までやらないといけない!」
となってしまい、受験勉強に集中できなくなってします。
転向するならば、なるべく早いタイミングの方が、軌道修正はしやすくなります。
文転・理転どちらが難しい?
高校3年生の入試直前に転向する受験生もいないわけではありません。
たとえば国公立理系から経済学部へ切り替える場合、共通テストはそのまま「社会1科目+専門理科2科目」で受けられる大学もあり、二次試験も文系生徒が苦手にしやすい数学で受験できる形式であれば、大きな不利もなく文転はできるでしょう。
逆に文系から理転する場合、工学部などでは二次試験で数Ⅲまで必須な大学が多く、共通テストでも専門理科2科目の形式をとっていることが多いため、負担は大きく増えてしまいます。
「理転よりも文転の方がしやすいから、迷っているなら最初は理系を選択しておくと良い」と言われる通り、単純な負担や合格可能性で考えれば、「文転よりも理転の方が難易度は高い」という結論になるでしょう。
文転・理転を成功させた先輩の共通点
難しいといわれる「理転」ですが、高校3年生のタイミングで理転して、第一志望に合格している先輩たちもいます。
彼らに共通しているのは、「高2までの復習を徹底的に行っていた」ということ。文系でも高2までに数ⅠAⅡBを習うため、そこまでの知識が固まっていれば3年生からは数Ⅲの対策に時間を割けます。理科も基礎範囲ができていれば、専門理科にかける時間も理系生徒と大きな差が生じません。
つまり、「将来の道が不安」「どう進んでいけば良いのかわからない」という人ほど、今習っていることを完璧にすることで、自分の選択肢が広がっていくのです。
受験に必要な科目
2025年度から入試が変わる!
「2022年度時点で高校1年生」の代から、新学習指導要領がスタートし、共通テストの出題範囲が変わります。
注意点や細かい変更点などはこちらの記事にもまとめているので、確認しておきましょう。
現在高校2年生の人も、万が一もう1年…となった場合には適用となってしまうため、現役で志望校に合格できるよう、しっかりと準備しておく必要があります。
①現行の共通テスト ②2025年度以降の予定
【英語】① リーディング・リスニング
② 大きく変更なし
【国語】① 現代文・古文・漢文
② 大きく変更なし
【数学】① 数ⅠA・数ⅡB
② 数ⅠA・数ⅡBC
【理科】① A.基礎2科目 B専門1科目 C基礎2科目+専門1科目 D専門2科目
② 大きく変更なし
【社会】①〈地歴〉世界史B/日本史B/地理B 〈公民〉現代社会/倫理/政治経済/倫理・政経
② 各科目にそれぞれ歴史総合・地理総合・公共が必修科目として加わり、範囲が拡大
【情報】2025年度より新設
文系
受験で使用する科目の基本パターンは以下の通りです。
実際は志望校によって異なるため、現時点で気になる大学がある場合は、それぞれ調べてみましょう。
国公立文系【共通テスト】英語・国語・数学(2科目)・社会(2科目)・理科(基礎2科目)
【+二次試験】英語・国語+社会 or 数学(数Ⅲは除く)
私立文系 【一般試験】英語・国語+社会 or 数学(数Ⅲは除く)
理系
受験で使用する科目の基本パターンは以下の通りです。
実際は志望校によって異なるため、現時点で気になる大学がある場合は、それぞれ調べてみましょう。
国公立理系【共通テスト】英語・国語・数学(2科目)・社会(1科目)・理科(専門2科目)
【+二次試験】英語・数学・理科(専門1 or 2科目)
私立理系 【一般試験】英語・数学・理科(専門1 or 2科目)
各科目の文系・理系の違い
文系コース、理系コースに分かれると、各科目の履修範囲や授業進度が変わってきます。具体的に科目ごとにどのような違いがあるのか、確認してみましょう。
英語
文系・理系問わず、大学入試において最重要科目とされることも多い英語。英語は大学に進学した後も、必修科目となっている大学がほとんどです。したがって、将来のためにも英語を学んでおいて損はありません。
「最重要科目」とされている通り、英語が得意科目になっていれば、もしも模試の総合成績や志望校判定が芳しくない場合でも、最後まであきらめずに戦い続ける気持ちを保ちやすく、逆転合格を果たす現役生が多い、というのも事実。
つまり、英語は早期に基礎固めをしておくべき科目であり、絶対におろそかにできない科目といえるでしょう。
共通テストの注意点
共通テストでは、英語は「リーディング」「リスニング」を受験します。リーディングとリスニングの配点比率は大学によって異なるため、注意が必要です。
基本的には、リーディングとリスニングの配点比率は、4:1もしくは3:1の設定が多いのですが、北海道大学や一橋大学のように、リーディング:リスニングを1:1に設定している大学もあります。
したがって軽視できないリスニング対策ですが、「ただ英語の音声を聞く」というだけでは、共通テストには対応できません。本番では、矢継ぎ早に流れる英語の音声を、頭の中で瞬時に処理することが求められます。それに対応するための練習が必須ですから、「共通テストのリスニング対策」という時間を集中して、かつ定期的に確保しておくべきでしょう。
文理選択で気をつけるべきポイント
英語の大学受験対策において、文系・理系による差はないといえるでしょう。いずれを選んでも、大学入試において英語は「最重要科目」になることが多いためです。英語に苦手意識を持っている人は、最優先で対策しましょう。
国語
現代文の注意点
「現代文は日本語なので対策しなくても良い」と考えてしまっている人は、非常に危険です。特に、成績には波があるけど学校の定期試験では良い成績をとれる、という場合には、学習を後回しにしてしまいがちです。しかし、高校の授業で読んだことのある文章から出題される定期試験ではなく、緊張感と時間制限がある中で初見の文章を読解していく入試問題ですから、難易度は大きく高まります。
「現代文」では、現在までに発行されている膨大な量の書籍のうち、どの作品から出題されるか、予想をすることはまず無理ですから、ほかの科目のように「これは見たことがある問題だ!」という経験はほとんどないかと思います。
そのため、どんな文章が出題されたとしても、正しくかつスピーディに把握・理解するための「読解力」を意識的に鍛えていく必要があります。
古文の注意点
一方で古文については、古くは奈良時代の風土記から、150年前の江戸後期までの長い年月をかけて研究されてきた学問です。大学入試問題においては、ある程度決まった作品からの出題がされる傾向にあり、学校の授業や模試などでも頻繁に登場する作品があります。
漢文の注意点
漢文も同様で、正しい知識を早いうちに身につけておけば、安定した得点源になる科目です。国語の成績がなかなか上がらないという人は、まず確実な得点源を確保するために、「古文・漢文」から対策していくのも良いでしょう。
私立大学の一般入試においては、漢文を除く「現代文」「古文」の出題がほとんどです。早稲田大学全学部、難関大学の文学部など一部の入試では、漢文も範囲に含まれますが、共通テストを大きく上回るレベルで出題されることは少ないようです。
漢文の大学入試対策においては特に、基礎を押さえていくことが大切です。
文理選択で気をつけるべきポイント
国語については、共通テストで必要な学習範囲が変わりません。国公立文系では二次試験で国語が必須になることが多く、難関大では、数百字の論述や要約が出題されることもあります。その場合は、読解力だけでなく、記述力も磨いていく必要があります。志望大学の過去問題などを確認しながら、求められる力や形式は、あらかじめ確認しておきましょう。
理系の場合、先にも述べたように「古文」「漢文」を盤石にしておくことで、模試の得点が安定します。早めに取り組めると良いでしょう。また、共通テストは科目を問わず文章量が多いという特徴がみられます。現代文で文章を読み取る力が鍛えられれば、共通テストのほかの科目に対しても、大いに力を発揮できます。
数学
文系と理系で、科目負担が最も異なる科目の1つが「数学」です。数学は、文理で履修範囲の差が非常に大きいため、数学が苦手な人にとっては、理系を選択するための大きな壁になります。
例えば、複素数平面など数Ⅲの分野は、理系の場合は国公立の二次試験や私立の一般試験において頻出であり、苦手とする受験生も多いようです。基本的には、高1で数ⅠA、高2で数ⅡB、高3で数Ⅲ(C)を学んでいくことになりますが、「ⅠAが理解できていないのにⅡBは急にわかるようになる」ということはまずありません。
数学に苦手意識がある人は、数ⅠA、場合によっては中学数学から復習することで、基礎固めを確実に行っていく必要があります。
高校による進捗の違いに注意
私立高校や進学校では、高1の間に数ⅡBの大部分を終わらせ、高2の早いうちから数Ⅲを授業で扱う、という場合があります。これは、受験直前期の演習量を確保するためです。当然ながら、学校の授業のペースが非常に速いため、途中で追いつけなくなる生徒もいます。しかし、数学は積み上げて理解するもの。「ⅠAが理解できていないが、ⅡBはわかる」ということはあり得ません。
自力で挽回して追いつくことは非常に難しいため、自宅での予習復習はもちろんですが、高校の進捗に合わせて指導してくれる予備校や塾で、補修をうまく活用できるとよいでしょう。
理科
理科も数学と同様、文系コースと理系コースとで、履修範囲が大きく異なり、大学入試でも出題範囲に大きな違いが出ます。
高校では、1年生から2年生で基礎を履修し、3年生から本格的に専門分野へ進む学校が多くあります。ただし、理系コースになった場合は、高校2年生から専門分野の授業を行う高校も少なくありません。
高校1年生で習った基礎科目を大学受験で使う場合、1年のブランクを経て、高3になって専門分野の学習をすることになります。高校2年生の時期でも定期的な復習をしておけるとよいでしょう。
共通テストの注意点
共通テストでは、文系は「理科基礎」と呼ばれる科目から2科目、理系は「専門理科」から2科目が必要です。「専門科目」よりも「基礎科目」の方が学習負担は少なく、「理科基礎」2科目の代わりに、「専門理科」1科目で受験できる大学もあります。
文理選択で気をつけるべきポイント
理科は「基礎」か「専門」かで、学習負担が大きく変わります。さらに、専門分野の全範囲を授業で扱い終わるのが、高3の秋から冬となる高校が多く、学校で習うのを待っていては圧倒的に演習量が不足します。そのため、理科は「現役生と浪人生との間で差がつきやすい科目」と言われています。
受験に必要な場合には、学校の進捗を十分に考慮して、勉強スケジュールを立てていきましょう。
地歴公民
用語や年代を「単に覚えるだけ」では、入試問題には太刀打ちできません。
例えば、「その出来事が前後の時代にどんな影響を与えたか」「同じ年代にそれぞれの国では何が起きていたか」など、タテ軸・ヨコ軸を意識して歴史の流れをおさえましょう。
社会科は「暗記科目」と考えるのではなく、これまでの学習で身につけた能力や発想をさらに膨らませて問題に取り組む必要性がありますので、内容を十分に理解することにより意識を置きましょう。
文理選択で気をつけるべきポイント
国公立大学の文系学部では、共通テストにおいて2科目の受験が求められるケースが多くあり、地歴・公民からそれぞれ1科目ずつと決められている大学もあります。
東京大学のように二次試験で世界史+日本史の受験を必須としている大学もあるため、理科と同様、志望校の方式を把握した状態で科目選択をしましょう。
行きたい大学へ行くために
ここまで、高校における「文理選択」について、受験科目や科目負担について確認してきました。
大学では4年、または6年かけて将来に向けて学び、そして職業に就く準備をしていきます。大学を妥協して選んでしまい、後悔する受験生も少なくありません。苦手科目があるから、科目数が多くて大変そうだから、といった理由で、進みたい道を諦めてしまうのは非常にもったいないことです。
いずれの科目もまずは「基礎」を学び、理解の穴を埋めていきます。そのうえであなたの得意や好きなこと・興味のある方向へと伸ばしていきましょう。そうすることで行ける大学、ではなく「行きたい大学」への道が開けます。
大学の情報を集めよう
大学には様々な学部・学部が存在しています。同じ学部名でも、大学によって学ぶテーマや環境が異なっていることもあります。自分の進路を決めるためには、まずは情報収集からです。
四谷学院では「学部学科がわかる本」として、各学部の授業内容や主な進路をはじめ、卒業後の進路やよくある質問について、わかりやすくまとめています。
こちらのWebサイトからも見られるので、進路に迷っている人はぜひ参考にしてみてくださいね。

また、「学校で扱ってくれない科目がある」「学校に通わず高認を取得して大学合格を目指したい」という人たちも、四谷学院では、基礎の基礎から学習することができるので、あなたの力になれると思います。
もしも文理選択で悩んでいるのであれば、個別相談会に参加してみてください。ホームページから簡単にお申込みいただけます。Zoomでも参加可能です。