大学受験では、古典文学史に関わる出題もされますが、苦手にしている受験生も多いと思います。
必要なのはわかっているけど、全然覚えられない!
と苦しんでいる受験生もいますが、丸暗記しようとしていませんか?
古典文学史の覚え方
文学史を覚えるにはコツを押さえる必要があります。
文学史が出たら確実に得点できる!満点が取れるようにしっかり学んでいきましょう。
▼近代文学史はこちら

【大学入試対策】現代文の攻略!近代文学史の学習法は?何をチェックすればいい?
先生からひと言 「覚えなければいけない」「暗記しなければダメ」で終わらずに、傾向と対策を意識しましょう。 今回のように、自分の志望校で出題されやすい作家・作品の...

生徒
いや、古典文学史の表をいつも見てるんすけど、なっかなか覚えられないっすねー。

先生
そうだよね。ただ超重要な作品や成立年が覚えやすいものは丸暗記すべきだね。
たとえば、「大鏡」は1111年だから覚えやすい。「方丈記」も1212年、「徒然草」は1331年で、これらも超重要かつ比較的覚えやすいよね。
たとえば、「大鏡」は1111年だから覚えやすい。「方丈記」も1212年、「徒然草」は1331年で、これらも超重要かつ比較的覚えやすいよね。

生徒
けど、丸暗記だときついっす-。

先生
ええとね。影響関係ってのがあって、それをいちど覚えると忘れにくいよ。主要な作品の成立年の前後関係が分かるというのが重要だよね。
たとえば、「大和物語」は「伊勢物語」の影響を受けて成立していて、「大和(現在の奈良県)」の名は「伊勢(現在の三重県)」に対する命名であると言われているんだ。だから伊勢→大和。また、姫君が継母からいじめにあうことで有名な「落窪物語」は「源氏物語」に影響を与えているし、「枕草子」にも言及が見える。
たとえば、「大和物語」は「伊勢物語」の影響を受けて成立していて、「大和(現在の奈良県)」の名は「伊勢(現在の三重県)」に対する命名であると言われているんだ。だから伊勢→大和。また、姫君が継母からいじめにあうことで有名な「落窪物語」は「源氏物語」に影響を与えているし、「枕草子」にも言及が見える。

生徒
おお!

先生
したがって、落窪→源氏・枕(二つはほぼ同時期の成立)。「栄花物語」は後の四鏡と呼ばれる歴史物語の下地となったし、四鏡については、これは「だいこんみずまし」のゴロ合わせで知られているよね。
だから、栄花→大鏡→今鏡→水鏡→増鏡。
だから、栄花→大鏡→今鏡→水鏡→増鏡。

生徒
だいこんみずまし・・・
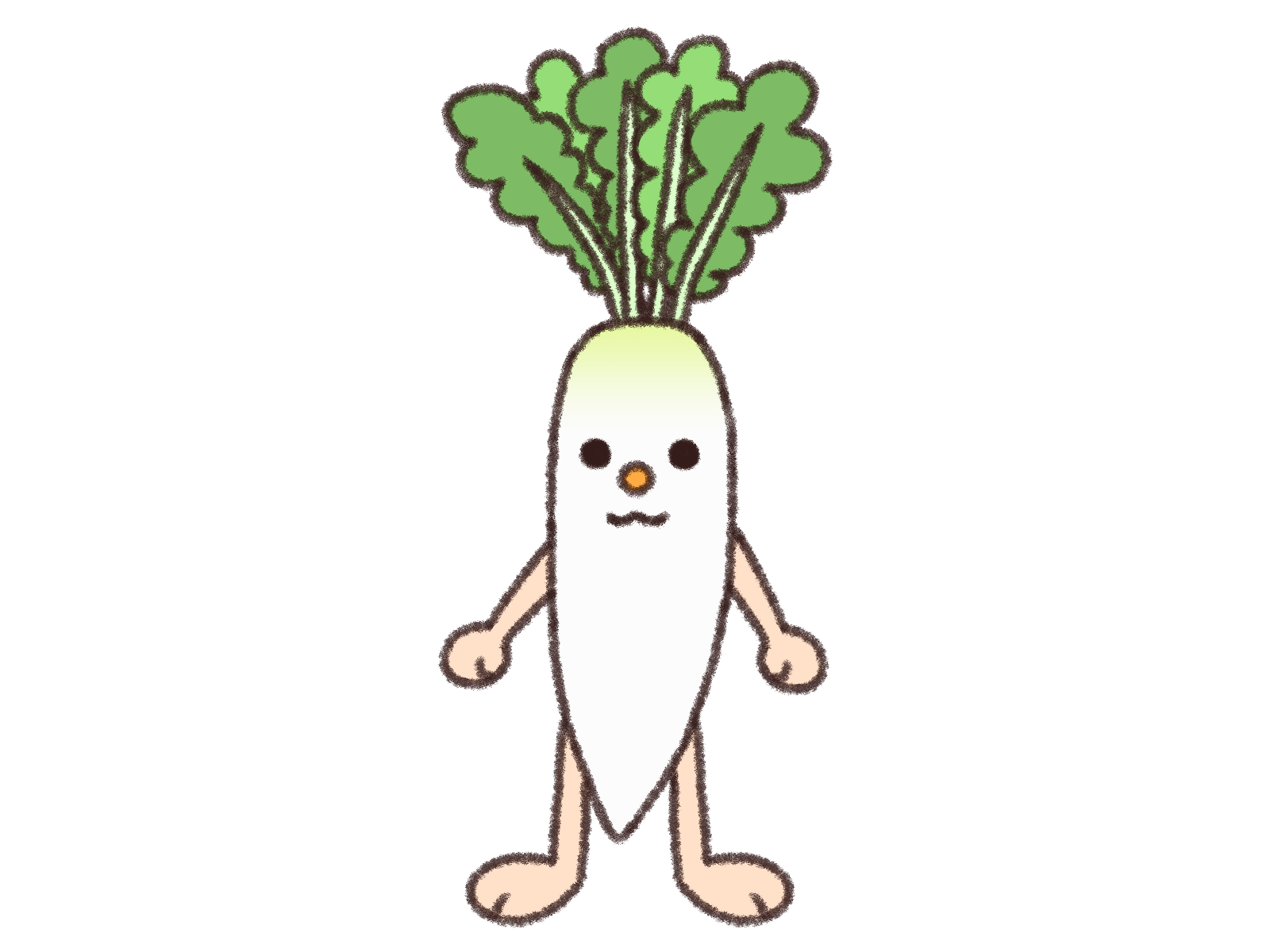

先生
ゴロ合わせでは、勅撰集なんかも、「この55(ご じゅう ご)の教室では金曜 しか 洗剤を新しくしない」
(古今集→後撰集→拾遺和歌集→後拾遺和歌集→金葉集→詞花集→千載集→新古今集)
なんて覚え方もあるから活用してみてねー。
(古今集→後撰集→拾遺和歌集→後拾遺和歌集→金葉集→詞花集→千載集→新古今集)
なんて覚え方もあるから活用してみてねー。

生徒
四谷学院の55段階個別指導の教室が登場するですね!!おーーっなんか全体像が見えてきました。了解っす!
古典文学史の不安を一掃!語呂合わせで楽に覚える
ゴロ合わせはイメージを膨らませるのにとても便利です。前後関係が分かると、中身の理解も深まりますから、「古典文学史なんてキライ」と毛嫌いせずにぜひチャレンジしてみてくださいね。
四鏡
四鏡は、「栄花物語」は後の歴史物語の下地。スタート!「栄花」だいこんみずまし
(1)大鏡 だい
(2)今鏡 こん
(3)水鏡 みず
(4)増鏡 まし
勅撰集
勅撰集は「この55(ご じゅう ご)の教室では金曜 しか 洗剤を新しくしない」
(1)古今集 この
(2)後撰集 ご
(3)拾遺和歌集 じゅう
(4)後拾遺和歌集 ご (の教室では)
(5)金葉集 きんよう
(6)詞花集 しか
(7)千載集 せんざい(を)
(8)新古今集 あたらしくしない

古典文学史が出題されたら確実に得点できるようにしっかり学んでいきましょう。


