
こんにちは、四谷学院の日本史担当、内藤です。
日本史の近現代史は覚えることが盛りだくさんです。苦手な受験生は多いのですが、実は入試でも頻出分野。近現代史を攻略すれば得点に直結します。
そこで今日は、日本史の近現代史を学習する上でのポイントを3つ紹介します。
ぜひ参考にしてください。
①ポイント政治外交史の軸を押さえる
まずは、最優先として、政治外交史の軸を確実におさえていきましょう。
明治以降の時代の流れを、政治外交史によって覚えていきます。まずは大枠から押さえます。
特に年号まで覚えるべきは、以下の項目です。
1867年 大政奉還 「一夜むなしい(1867)大政奉還」明治時代のはじまりです。
1885年 内閣制度創設
1889年 大日本帝国憲法発布
1894年 日清戦争 戦争は人を死(4)なせるむごいもの
1904年 日露戦争 日清戦争から10年後
1914年 第一次世界大戦 日露戦争から10年後
1919年 ヴェルサイユ条約
1931年 満州事変
1937年 日中戦争 「いくさ長引(1937)く日中戦争」
1945年 終戦
1951年 サンフランシスコ平和条約
1956年 日ソ共同宣言、国連加盟
1965年 日韓基本条約
1972年 沖縄返還・日中共同声明
1885年 内閣制度創設
1889年 大日本帝国憲法発布
1894年 日清戦争 戦争は人を死(4)なせるむごいもの
1904年 日露戦争 日清戦争から10年後
1914年 第一次世界大戦 日露戦争から10年後
1919年 ヴェルサイユ条約
1931年 満州事変
1937年 日中戦争 「いくさ長引(1937)く日中戦争」
1945年 終戦
1951年 サンフランシスコ平和条約
1956年 日ソ共同宣言、国連加盟
1965年 日韓基本条約
1972年 沖縄返還・日中共同声明
こちらの記事もぜひ参照してください。
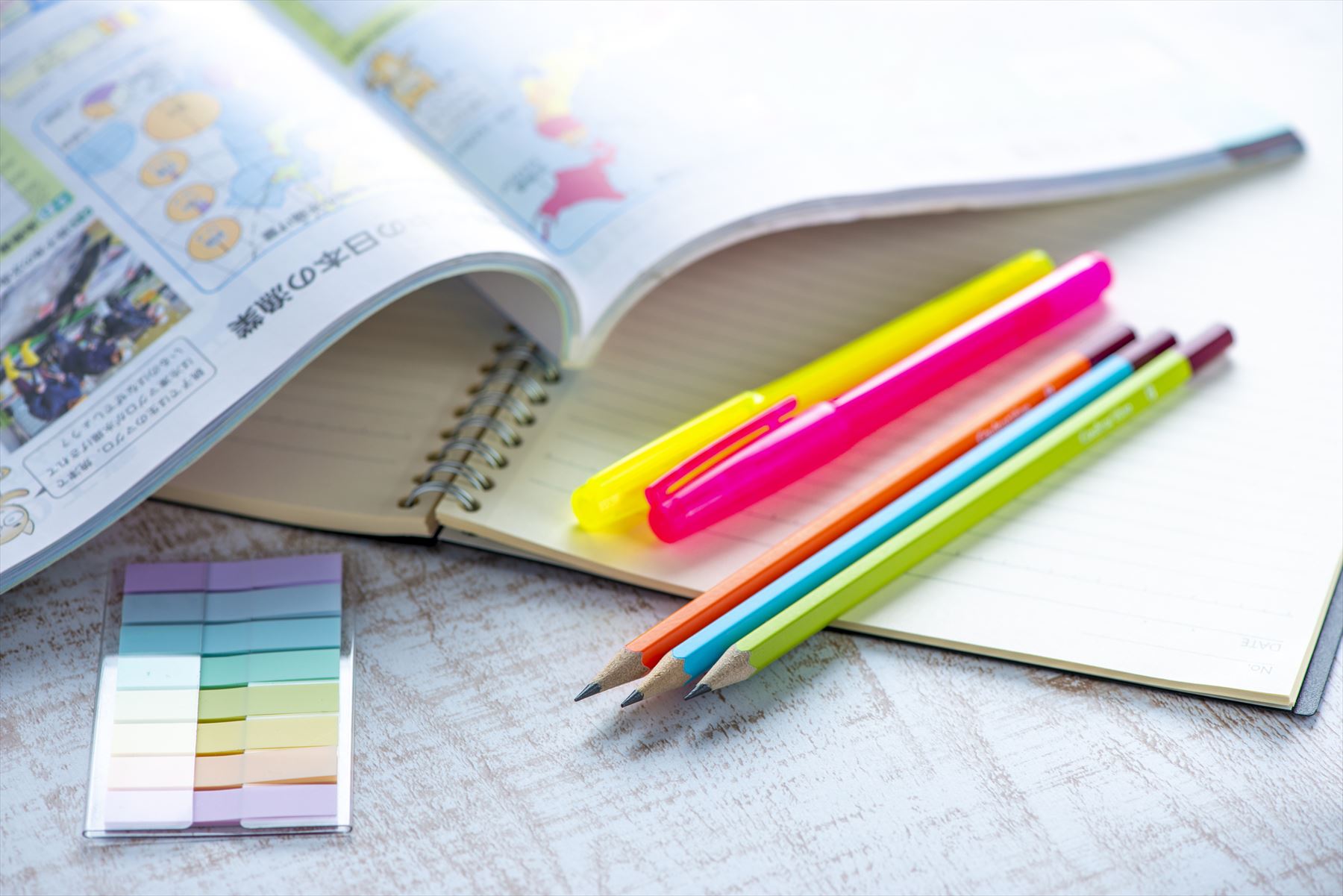
【ゼロから始める大学受験】日本史の勉強法と学習のコツ5箇条とは?文転・高1・高2は必見です
こんにちは、四谷学院の武田です。今日は、これから大学受験の学習をする人に向けて、日本史の勉強の仕方について解説していきます。 日本史の学習をするにあたって、以下...
ポイント②10年ごとに時代をイメージする
次に、10年ごとの区切りで、どんな時代だったのかのイメージを作っていきます。
ポイント①の政治外交史と関連付けてイメージを作りましょう。
【イメージ例】
1870 明治維新の改革が進む
1880 内閣、憲法が整備される
1890 日清戦争前後
1900 日露戦争前後
1910 第一次世界大戦
1920 国際協調の時代
1930 軍国主義化への傾斜
1940 第二次世界大戦 戦前・戦後
1950 日本の独立・55年体制
1960 高度経済成長・韓国と国交樹立
1970 石油危機・中国と国交樹立
1980 中曽根内閣
1870 明治維新の改革が進む
1880 内閣、憲法が整備される
1890 日清戦争前後
1900 日露戦争前後
1910 第一次世界大戦
1920 国際協調の時代
1930 軍国主義化への傾斜
1940 第二次世界大戦 戦前・戦後
1950 日本の独立・55年体制
1960 高度経済成長・韓国と国交樹立
1970 石油危機・中国と国交樹立
1980 中曽根内閣
ポイント③内閣の順番を覚える
学習が進んだら、内閣の順番を覚えてしまい、出来事を再整理するといいでしょう。内閣の順番を覚えて、重要事項と結びつけていきます。
「いぐろやま、まいまい、おおやまい」これだけで明治の最初の10の内閣の順番が覚えられます。
こちらの記事で具体的に紹介しています。

日本史受験者に必須!内閣総理大臣の覚え方。政権担当の順に覚えるコツ
こんにちは、四谷学院の山中です。 「日本史」を受験する方にとって押さえておきたい内閣総理大臣の覚え方について紹介します! 政権担当の順番が分かれば、それぞれの人...
1つの内閣について、まずは1つでいいので、代表的な出来事を結び付けられるようにすると、時代の流れがイメージしやすくなるはずです。
まとめ:大学入試に頻出!日本史「近現代史」苦手克服の勉強法

今日は日本史の近現代史を勉強していく上での入門部分を紹介しました。
近現代史は覚えることがたくさんあり、やみくもに覚えようとしても知識が定着しません。まずは時代の枠組みをしっかりとつくり、そのうえで前後の出来事との関連付けをしながら細部を覚えていきましょう。
四谷学院では夏期講座で「近現代史入門」講座を設置しています。
学習の指針を明確にして、難敵に対して戦略的に挑みましょう!



