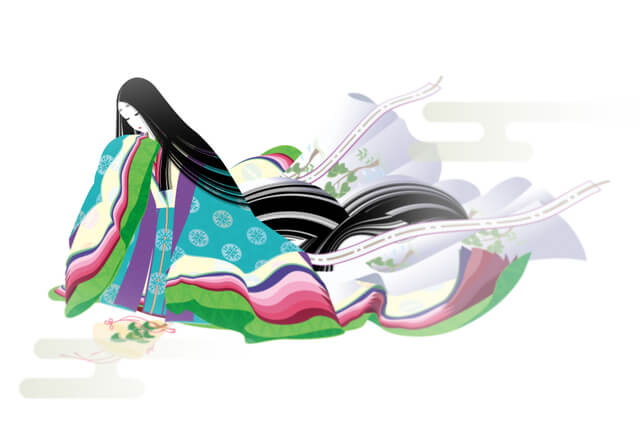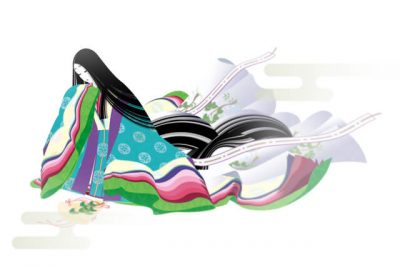
こんにちは、四谷学院の山中です。
古文を勉強していると、現代でも使われている単語がたくさん出てきますよね。
同じ日本語ですから、当然と言えば当然なのですが…現代語とまったく違う意味になっている言葉もあるので、要注意です!
はやう見し女?
古文単語が現代語と全く別の意味になることは多くあります。
例えば「枕草子」の「にくきもの」という章段から引用すると…
わが知る人にてある人の
はやう見し女のことほめ出でなどするも
ほど経たることなれど
なほにくし。『枕草子』より
現代語に訳してみましょう。
「自分と今関係している男が
以前関係のあった女のことをほめて話し出すのも
年月が過ぎたことではあるが
やはり憎らしい。」
え?そんなコイバナしていますか?
現代語と同じように考えてしまうと
「私の知っているあの人が、早く見た女性のことをほめて話し出すのも、年月が過ぎたことではあるが、なおさら憎らしい。」
という感じになりますよね?
話が全然違います。
「知る」「はやう(早う)」「見し(見る+過去の助動詞「き」)」「なほ」
これらは現代語とは全く異なる意味として使われているんですね。
同じ日本語だから…と思いがちかもしれませんが、全く違う意味を知って「へ~、なるほど~」と思うことも多いと思います。
1つずつしっかり覚えて、正しく内容を把握できるようにしておきましょう。
こちらの記事も参考にしてくださいね。

古文が苦手なキミ!古文単語を覚える裏ワザ
こんにちは、四谷学院の山中です。 古文の勉強をしていて「この単語覚えられない、はあ・・・」と思ったことはありませんか? そんなとき役に立つ古文単語を覚える裏技を...

【古文読解】古文の常識!仏教思想・仏教の影響とは?大学受験対策古文
大学受験の古文では、仏教がテーマになっていることがあります。例えば、登場人物が出家しようとしていたり、主人公や重要人物が僧だったり。古文常識として仏教は欠かせま...