
こんにちは!四谷学院の奥野です。
東京理科大学は、東京都新宿区に本部を置く理系の私立大学。
1881年創設の東京物理学講習所(1883年に東京物理学校に改名)が前身となっており、自然科学系の高等教育機関としては国内で2番目、私立では最古の歴史を持っています。
理学部や工学部など7学部を擁し、唯一の文系として経営学部も設置されています。
この記事では、東京理科大学の入試の特徴や難易度、倍率、合格するための効率的な勉強方法を紹介します。
東京理科大学の受験を考えている方、勉強しているのに成績が伸び悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
※本記事に記載されている情報は2023年11月9日現在のものです。最新の情報は大学公式ホームページにて必ずご確認ください。
目次
東京理科大学の概要
東京理科大学は、私立大学でも最大規模の学部・学科と豊富な研究領域を展開している理系総合大学です。国際化や海外留学にも力を注ぎ、奨学金制度も充実しています。
7つの学部と33の学科を有し、キャンパスは神楽坂と野田、葛飾、そして北海道・長万部の4箇所に構えています。
また、大学院生や学部生が数多く受賞しており、ともに切磋琢磨しながら研究を進めています。
設立年:1881年
学生数: 19,768人(2023年5月1日時点)
所在地:
・神楽坂キャンパス
[神楽坂校舎] 〒162-8601 東京都新宿区神楽坂1-3
[富士見校舎] 〒102-0071 東京都千代田区富士見1-11-2
・野田キャンパス
〒278-8510 千葉県野田市山崎2641
・葛飾キャンパス
〒125-8585 東京都葛飾区新宿6-3-1
・北海道・長万部キャンパス
〒049-3514 北海道山越郡長万部町字富野102-1
大学紹介ムービー:
公式ホームページ:東京理科大学
Facebook:東京理科大学/Tokyo University of Science
Instagram:tokyouniversityofscience
X(旧Twitter):@TUS_PR
You Tubeチャンネル:東京理科大学/Tokyo University of Science
東京理科大学の学部別偏差値と難易度(レベル)
Benesseの「マナビジョン」のデータでは、2023年11月9日現在の東京理科大学の入試の偏差値は50~72、大学入学共通テストの得点率は57~87%となっています。
なお、学部ごとの偏差値は以下のとおりです。
| 学部 | 偏差値範囲 |
| 経営学部 | 60~68 |
| 理学部第一部 | 63~66 |
| 理学部第二部 | 50~55 |
| 工学部 | 60~65 |
| 創域理工学部 | 58~63 |
| 先進工学部 | 60~63 |
| 薬学部 | 63~65 |
理学部第二部以外の学部は偏差値60を超えており、難易度が高いといえるでしょう。GMARCHと同程度の難易度であるため、十分な対策をして受験に臨む必要があります。
東京理科大学と近い偏差値・難易度(レベル)の大学
ここでは、東京理科大学と近い偏差値・難易度(レベル)の理系大学をいくつか紹介します。
■偏差値の近い大学「経営学部」
中京大学 経営学部(偏差値55~62)
愛知大学 経営学部(偏差値52~60)
駒澤大学 経営学部(偏差値56~62)
■偏差値の近い大学「理学部」
関東学院大学 理工学部(偏差値43~53)
日本大学 理工学部(偏差値50~60)
東海大学 理学部(偏差値46~51)
■偏差値の近い大学「工学部」
芝浦工業大学 工学部(偏差値53~63)
関西大学 環境都市工学部(偏差値55~67)
関西学院大学 工学部(偏差値56~62)
■偏差値の近い大学「薬学部」
星薬科大学 薬学部(偏差値59~63)
東京理科大学 薬学部(偏差値63~65)
立命館大学 薬学部(偏差値56~63)
東京理科大学入試の特徴
東京理科大学の選抜方式は幅広く用意されていますが、大きく分けると以下のようになります。
一般選抜
東京理科大学で、最も受験者数が多い選抜方式です。一般選抜のなかに次の5つの方式があります。
- A方式:大学入学共通テストを利用した全学部対象の方式
- B方式:全学部対象で、大学独自の入学試験が実施される方式
- C方式:昼間学部対象で、大学入学共通テストと大学独自の試験を併用する方式
- S方式:創域理工学部の一部学科が対象で、大学独自の試験を実施する方式
- グローバル方式:昼間学部対象で、指定の英語資格・検定試験のスコアが出願資格となり、大学独自の試験を実施する方式
学校推薦型選抜
推薦を依頼する高校を指定する「指定校制」と、高校からの推薦に基づき広く選考を受け付ける「公募制」の2種類があります。
その他の選抜方法
帰国生入学者選抜や国際バカロレア入学者選抜など、その他の選抜方法もあります。
上記以外の選抜方法と入試の詳細については、募集要項(PDF)や東京理科大学ホームページの入試情報でご確認ください。
東京理科大学の入試科目別の出題範囲とその対策
東京理科大学の入試対策では、独自試験の問題の特徴や傾向をつかんでおくことが大切です。理系の総合大学のため、受験科目は数学、英語、理科(科目選択)が基本。
注意が必要になるのは、東京理科大学の独自試験では、学部・学科ごとに出題範囲問題が異なる点です。
したがって、東京理科大学では過去問題などを活用して学部・学科に応じた対策が必要になります。
ここでは、受験者数が多い一般選抜B方式の試験問題の傾向を、科目ごとに紹介します。
英語の対策と勉強法
英語の試験時間は、理系学部では60分、経営学部では80分です。理学部第一学部ではマークシート方式、工学部はマークシート方式と記述式の併用、経営学部ではマークシート方式と、学部や学科によりばらつきがあります。
東京理科大学の英語は、長文問題が中心に構成されています。設問文などもすべて英語のため、長文の速読力が必要でしょう。
長文問題以外では、文法や語彙をしっかり身に付けておくことが大切です。
数学の対策と勉強法
理系学部の数学の試験時間は100分、経営学部では必須の数学だと60分、選択科目の数学だと100分です。
理系学部では数学Ⅲまでが範囲に入っており、微分積分が頻出傾向にあります。
とはいえ、すべての範囲からまんべんなく出題されるため、網羅的に学習を進める必要があるでしょう。
経営学部では数学Ⅱ・数学Bまでの範囲で、幅広く出題されるため頻出分野がなく、基礎的な知識を必要とする問題が多いとされています。
教科書の内容を中心に勉強し、基礎固めをすることが大切です。
国語の対策と勉強法
理系学部では国語のテストはなく、経営学部のみで対策が必要な科目です。
学科により、必須になっている場合と選択科目の一つになっている場合があります。試験時間は100分、マークシート方式と記述式の併用です。
出題される評論は1題の分量が多く、難易度はやや難しいレベルとされています。
試験時間内に解き切るためには、読解速度や解答速度を高める必要があります。過去問などさまざまな文章を使って、十分なトレーニングを積んでおきましょう。
理科の対策と勉強法
理系学部では、物理・化学・生物から1科目を受験します。試験時間は80分です。学科により受験科目が指定されている場合と、自分で1科目を選択する場合があります。
ただし理学部第一部数学科と応用数学科、理学部第二部数学科は、数学を2回受験するので、理科の受験科目はありません。
物理では、思考力を必要とする問題が出されます。そのため、各分野の原理などを理解して、きちんと使えるようにする必要があります。
化学では基本知識を問われるほか、計算問題が多く出されるので、素早く解く力が必要です。
生物では、細胞や遺伝子、植物などに関する出題が多くみられます。全体的にレベルが高いため、基礎固めをしたうえで応用問題の演習も進めておきましょう。
東京理科大学の入試概要

ここからは、東京理科大学の入試概要を解説します。
出願資格について
東京理科大学の出願資格は選抜方式ごとに定められているため、ここでは一般選抜における出願資格を紹介します。
- 高等学校(特別支援学校の高等部を含む)または中等教育学校を卒業した者および入学年の3月卒業見込みの者
- 高等専門学校第3学年修了者または入学年の3月修了見込みの者
- 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者および入学年の3月31日までにこれに該当する見込みの者
上記のうち、3つめの条件で受験する場合には、さらに詳細な条件が定められているため、必ず選抜要項を確認しましょう。
入試日と出願の受付期限
2024年度の入試に関して、一般選抜の募集要項は2023年11月中旬に公開予定のため、過去の情報をもとに紹介します。
出願期間は例年、1月頭〜中旬もしくは2月中旬までで、試験日は2月頭です。受験する学部や方式によって異なるため、詳細は募集要項を確認してください。
一般選抜以外の選抜方法の募集要項は、東京理科大学ホームページから確認できます。
なお、大学入学共通テストの出願日は9月25日(月)〜10月5日(木)で、試験は2024年1月13日(土)と1月14日(日)に行われます。
入試科目や合格要件
東京理科大学の学部ごとの試験科目や配点は、以下のようになります。ここでは、参考として一般選抜B方式を取り上げます。
なお、以下のデータはすべて2023年11月9日現在のものです。
B方式
B方式は、大学の独自問題を受験する選抜方法です。必要な受験科目は、次のようになっています。
なお、理科の必須科目や選択科目、学科ごとの配点など詳細は、東京理科大学一般選抜要項(PDF)でご確認ください。
| 教科 | 科目 | 備考 |
| 数学 | 「数学Ⅰ」「数学Ⅱ」「数学Ⅲ」「数学A」「数学B」 | 経営学部は学科により選択科目として選べる場合あり ※経営学部の必須科目である数学には「数学Ⅲ」は含まれない |
| 英語 | 「コミュニケーション英語Ⅰ」「コミュニケーション英語Ⅱ」「コミュニケーション英語Ⅲ」「英語表現Ⅰ」「英語表現Ⅱ」 | リスニング、スピーキングは課さない |
| 理科(理系学部のみ) | 「物理(物理基礎、物理)」「化学(化学基礎、化学)」「生物(生物基礎、生物)」 | 学部・学科により1科目選択の場合と、指定された1科目を受験する場合がある |
| 国語(経営学部のみ) | 「国語総合(古文、漢文を除く近代以降の文章)」「現代文B」 | 学科により必須の場合と選択科目の一つになっている場合がある |
出願者数や合格者数のデータ
東京理科大学の出願者数や合格者数は、以下のとおりです。なお、ここで紹介するデータは、2023年度一般入試B方式のものです。
| 学部 | 募集人数 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
| 理学部第一部 | 236 | 5,756 | 5,512 | 1,623 | 3.4 |
| 工学部 | 230 | 7,027 | 6,643 | 2,044 | 3.3 |
| 薬学部 | 80 | 1,579 | 1,468 | 505 | 2.9 |
| 創域理工学部 | 438 | 9,049 | 8,644 | 3,568 | 2.4 |
| 先進工学部 | 230 | 4,810 | 4,646 | 1,919 | 2.4 |
| 経営学部 | 177 | 2,570 | 2,493 | 786 | 3.2 |
| 理学部第二部 | 203 | 716 | 584 | 412 | 1.4 |
東京理科大学の受験料と学費目安
東京理科大学の受験料は、受験方式によって異なります。
一般選抜の各方式の受験料は、以下のとおりです。
| 選抜方式 | 受験料 |
| A方式 | 19,000円(1学科につき) |
| B方式 | 35,000円(同一試験日で2学科出願:55,000円) |
| C方式 | 35,000円(2学科出願:55,000円) |
| S方式 | 35,000円(1学科につき) |
| グローバル方式 | 35,000円(2学科出願:55,000円) |
入学金は理学部第二部のみ150,000円で、その他の学部が300,000円となっています。授業料と施設設備費を加えると、年間の支払総額は910,000〜2,300,000円です。
東京理科大学卒業後の進路
東京理科大学の卒業生のうち、50.8%(経営学部を除く昼間学部では60.2%、夜間学部では30.5%)が大学院へ進学しています。
就職した卒業生の約90%が一般企業に就職しており、なかでも情報通信業と製造業の割合が大きい傾向にあります。
東京理科大学が気になった人はオープンキャンパスや学校説明会へ
東京理科大学に興味を持った方は、オープンキャンパスや説明会へ積極的に参加しましょう。
参加すると、学校の雰囲気やカリキュラム、各学部の詳細について知れます。また、教員や学生への質問を通じて自身の疑問や不安を解決し、入学に向けて自信をつけられるでしょう。
オープンキャンパスや学校説明会の詳細はこちらから
東京理科大学に合格するための勉強方法
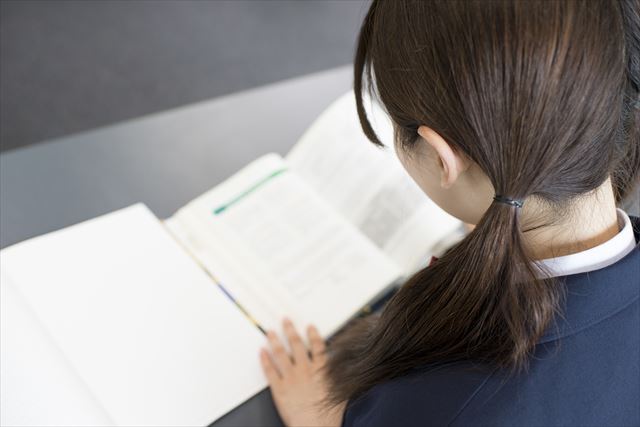
ここからは、東京理科大学に合格するための学習方法を紹介します。
東京理科大学に入るにはどのような対策をすればいい?
理系総合大学の東京理科大学の入試は、思考力や計算力を問われる問題が中心です。
第一志望で臨む受験生はもちろんのこと、早稲田や慶應、東工大などと併願する受験生も多く、ハイレベルな戦いになることが予想されるでしょう。
1つのミスが合否を分ける事態になりかねないため、基礎を徹底しつつ、演習をどれだけ積むか、どれだけミスをなくすかが重要です。解答を見直す癖をつけるようにして、ミスを減らす工夫をしましょう。
東京理科大学の入試では、出題範囲が学部・学科によって異なるため、過去問を使って対策をしておきましょう。
受験期の過ごし方と勉強のコツ
ただひたすら机に向かっているだけでは、効率よく成績を上げることは難しいでしょう。受験期で特に重要なのは、長期のスケジュールを立てて、計画的に学習を進めることです。特に高校3年生の1年間は、学習の進め方次第で合否の確率が変わる重要な期間。東京理科大学合格に向けて、下記を参考にスケジュールを立てましょう。
- 春(4〜5月):基礎を徹底して身に付ける期間です。教科書を中心に丁寧に学習し、基礎問題に取り組みましょう。基礎を確認することで、理解度が低かった分野や苦手分野の洗い出しにつながります。
- 夏(6〜8月):苦手分野に集中して取り組み、克服する期間です。夏休みには「1日に問題集を10ページ進める」などの短期的なスケジュールを組むのがおすすめ。まとまった学習時間を確保でき、落ち着いて取り組める時期なので、苦手分野の克服につなげましょう。
- 秋(9〜11月):大学入学共通テストの対策を始める時期です。独自試験のみでの受験を考えている場合でも、基礎知識の確認に役立ちます。大学入学共通テスト用の問題集などを活用しましょう。
- 冬(12月〜):独自試験対策として、過去問にしっかり取り組みましょう。東京理科大学の独自試験は、思考力や計算力を必要とする問題が多いとされています。時間配分に気を付けつつ、ミスなく問題を解くトレーニングをし、最後の仕上げをします。
東京理科大学を目指すなら予備校を使って入試対策をしよう
なかには、独学で受験勉強を進める人もいますが、受験情報を集める力や学習を計画的に進める意志が強くないと、継続は難しいでしょう。
そのため、独学での勉強に不安がある方は、予備校を利用するのがおすすめだといえます。
しかし一方で、「予備校に通っていれば問題ない」とも言い切れないでしょう。
一般的な予備校では集団授業が行われていますが、講師の話をただ聞いて終わるだけになると、知識が十分に定着しない場合があるからです。
また、苦手分野が取り残されやすいことも、集団授業のデメリットといえます。
授業でわからなかったところは自分で講師に聞きに行くなど、積極的に苦手分野と向き合わなければ、克服に十分な効果は期待できないでしょう。
このような、予備校の授業に生じやすいデメリットをカバーしてくれるのが、四谷学院の「ダブル教育」です。ダブル教育の2つのポイントをチェックしてみましょう。
科目別能力別授業
多くの予備校では、志望校やテストの総合得点でクラスを分けします。
そのため、苦手科目の授業についていけなかったり、得意科目の授業が物足りなかったりと「科目ごとのレベルの不一致」が起こることがあります。
四谷学院の科目別能力別授業は、科目と能力の2つでクラス分けするのが特徴です。
自分のレベルに合った授業を受けられるので、無理なく理解が進み、効率的に理解力向上を目指せるでしょう。
55段階個別指導
科目別能力別授業で得た理解を、解答力につなげるのが55段階個別指導です。
55段階個別指導では、過去の入試問題を徹底分析して作られた55テストにより、理解に穴があるところ、考え方が不完全なところ、表現が不適切なところをチェックします。
解答力が身に付いているかを確認しながら、級を進めていきます。
中1レベルから東大レベルまでの55段階をスモールステップで細かく確認していくことで、無駄なく解答力を磨けます。
東京理科大学入試は丁寧に解く力が重要!
【東京理科大学の入試概要】
- 理系の私立大学だが、経営学部も人気
- 大学入学共通テストや独自試験など複数の選抜方式
- 難易度は受験方式や科目により標準~難
【東京理科大学の入試データまとめ】
- 2023年度一般選抜B方式における実質倍率は1.4〜3.4倍。学部や学科により差がある。
【勉強方法まとめ】
- 独自問題は、同じ科目でも学部・学科で出題範囲が異なる
- 過去問対策をしっかり行い、志望学科の傾向をつかむ
東京理科大学は歴史ある理系総合私立大学で、第一志望で目指す人も多く、早稲田や慶應などと併願する人も少なくありません。ハイレベルな戦いになりやすい大学なので、十分な対策が必要になるでしょう。基礎を徹底したうえで、いかにミスを少なく抑えて問題を解くかが重要になってきます。そこでおすすめなのが、四谷学院の「ダブル教育」。
自分の学習レベルに合った授業で、効率的な成績向上が望めます。気になる方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
※本記事でご紹介した情報は2023年11月9日現在のものです。最新の情報は大学公式ホームページにて必ずご確認ください。
失敗しない予備校選びは説明会参加が重要!
予備校選びは、大学受験の合否に大きな影響を与えます。インターネットで確認できる情報だけでは限りがあるため、実際に説明会に参加して、自分に合った予備校を選びましょう。
以下の記事では、予備校の説明会について詳しく解説しています。説明会に参加する際の疑問や不安を解消するためにも、ぜひご一読ください。



