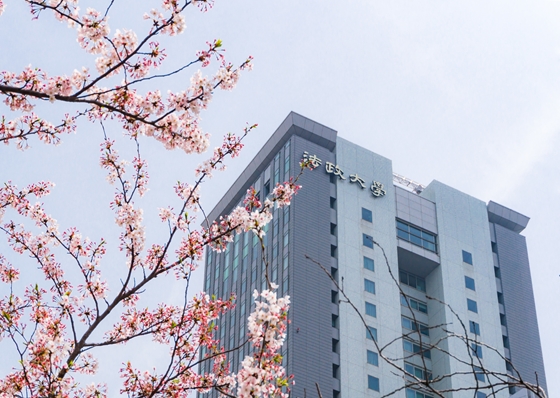関西の4つの名門大学の通称である「関関同立」。その一つである関西大学は多くの学部があり、他大学では学ぶことのできないことも学べると人気の大学です。受験者数が多いことでも有名なので、ライバルの多い関西大学に入学するためにはどのような受験対策が必要なのか、悩んでいる方は多いでしょう。
そこで本記事では、関西大学の受験資格や出願者などの各種データ、試験の難易度、求めている人材像などをご紹介。関西大学合格のための勉強方法も解説するので、関西大学に興味のある方、受験を予定している方はぜひ参考にしてみてください。
※本記事に記載されている情報は2022年12月22日現在のものです。最新の情報は大学公式ホームページなどで必ずご確認ください。
関西大学の入試問題で問われる能力

関西大学の入学試験で問われる能力とは、どのようなものでしょうか?ここでは、関西大学が求める人材、入試の特徴、入試の難易度から、必要な能力について探っていきます。
関西大学はどのような人材(学生)を望んでいるのか
関西大学は、関西初の法律学校として1886年に創立された大学。130年以上の歴史を誇り、「学理と実際との調和」を求める「学の実化」を理念として掲げて教育を行っています。
そんな関西大学のアドミッション・ポリシー(入学者受入方針)に挙げられているのは、以下の3つ。身に付けた知識を困難を克服するために使い、多様性を尊重できる人材が求められています。
1.高等学校の教育課程を通じて、基礎的な知識・技能を幅広く習得している。
2.高等学校の正課及び正課外での学習を通じて、柔軟な思考力、旺盛な知的好奇心、社会に貢献しようとする高い目的意識など、「考動力」の基盤を培っている。
3.特定の学問領域を主体的に学んでいく強い意欲を持っている。
出典:入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)
上記以外にも、関西大学は学部ごとにアドミッション・ポリシーが存在します。公式HPに記載されているので、そちらをチェックしてみましょう。
関西大学入試の特徴
関西大学入試の特徴は、入試方法の多様性。他大学でも一般的に行われている入試方法はもちろん、社会人や外国人留学生の編入試験も豊富に用意されています。自分の特性を活かして受験をすることができます。
ここでは、そのなかでも一般的に利用されることの多い入試方法を2つご紹介します。2020年度から新たな入試制度も導入しているので、必ずチェックしておいてください。
一般入試
最も受験者数の多い入試方法で、「全学日程1」「全学日程2」「学部独自日程(総合情報学部のみ実施)」の3種類があります。
特に全学日程は1度の試験で複数の学部・学科の合否が分かるので、できるだけ受験日を減らしたいという方にはぴったり。ただし、併願できる学部や学科は定められています。公式HPをチェックして、併願が可能かどうか確かめてみましょう。
一般入試では、指定の英語外部試験の基準を満たしていれば外国語の試験が免除される「英語外部試験利用方式」という入試方法が2017年度から導入されています。すでに基準を満たした資格や点数を獲得している場合は、大きなメリットを得られるのでチェックしてみましょう。
共通テスト利用入試
大学入学共通テストの結果で合否が判定される入試方法。共通テスト(併用)、共通テスト(前期)、共通テスト(後期)の試験があります。
共通テスト利用入試(併用)は、大学入学共通テストの得点と個別学力検査の得点で合否判定する方法です。前期は共通テスト前に出願しますが、併用型と後期は共通テスト後の出願も可能です。
併用型以外は個別の学力検査を行うことなく関西大学を受験できるので、大学別の受験対策の心配がないのが大きなメリット。しかし、滑り止めとして受験する人も多いので、レベルが高い競争になってしまう傾向にあります。
各科目の試験問題の特徴
それでは、関西大学の各科目の試験問題を以下で詳しく見ていきましょう。尚、学部や学科によって試験時間や配点、試験の難易度が大きく異なる場合があるので、ここでは全学部日程入試について解説致します。
英語
関西大学の英語は、全学日程・学部独自日程入試のどちらを選択しても問題形式は同じ。そのため、受験する学部や学科別に対策をする必要はありません。試験時間は90分で、配点は200点。大問3つで構成されており、解答はマーク式です。
3つの大問のうち2つは長文読解。難易度は標準レベルですが、読解力が必要となります。接続詞に注目することや、文構造を把握できるようにする対策を行いましょう。長文読解以外は基本問題が出題されるので、ミスなく解くことが要求されます。
国語
国語の試験時間は75分、配点は150点で解答はマーク式。現代文と古文の大問2つで構成されており、現代文は評論文や論説文であることがほとんどです。現代文の難易度は少し高め。特に選択問題で紛らわしいものが多く出題されるので、正しく読み解く力が求められます。対して、古文の難易度は易しめ。単語や古典文法を中心に学習しましょう。
数学
関西大学の文系数学は、試験時間が60分で大問3つ。配点は試験方式により異なります。マーク式と記述式のどちらの問題もあるのが特徴です。文系数学は基礎力が大切です。教科書を中心に基礎を固める学習をしましょう。
また、理系数学の難易度も近年易しくなっている傾向があります。過去問や青チャートを中心に学習しましょう。
関西大学入試の難易度
Benesseの大学受験・進学情報「マナビジョン」のデータでは、関西大学の入試の偏差値は56~74、共通テスト得点率は59~90%となっています。以下は、学部別の偏差値データです。
| 学部 | 偏差値 |
| 文 | 68~71 |
| 外国語 | 71~74 |
| 法 | 68~71 |
| 政策創造 | 65~70 |
| 経済 | 67~73 |
| 商 | 68~71 |
| 社会 | 66~71 |
| 総合情報 | 61~68 |
| 社会安全 | 64~68 |
| システム理工 | 57~63 |
| 化学生命工 | 57~67 |
| 環境都市工 | 56~67 |
| 人間健康 | 63~67 |
関西大学試験の概要
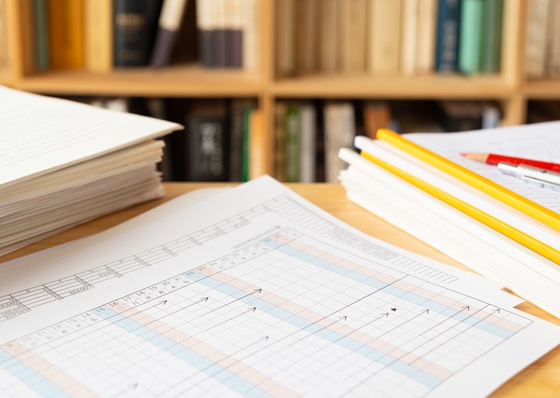
ここでは、受験資格や試験科目と合格要件、出願者数や合格者数のデータなど、関西大学の入試概要について見ていきましょう。
※記事に記載のデータは、2022年12月22日現在のものです。
受験資格について
多様性を重視している関西大学の受験資格は、以下の3つ以外にもたくさんあります。以下に当てはまらない場合は、公式HPをチェックしてみてください。
1.高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および入学年の3月卒業見込みの者。
2.通常の課程による12年の学校教育を修了した者および入学年の3月修了見込みの者。
3.学校教育法施行規則第150条の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、および入学年の3月31日までにこれに該当する見込みの者。
試験科目や合格要件
関西大学の学部ごとの試験科目や配点は、以下のとおりです。ここでは2023年度一般入試3教科型おける試験科目を、一部学部を抜粋して解説します。
参照:関西大学2023年入試ガイド(PDF)
法学部
| 教科 | 科目 | 配点 |
| 外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
| 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 150 |
| 地歴・公民または数学 | 世界史B、日本史B、地理B、政治・経済、数学(数学Ⅰ・Ⅱ、数学A・B〈数列・ベクトル〉)のうちから1科目選択 | 100 |
| 総合計 | 450 | |
文学部
| 教科 | 科目 | 配点 |
| 外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
| 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 150 |
| 地歴・公民または数学 | 世界史B、日本史B、地理B、政治・経済、数学(数学Ⅰ・Ⅱ、数学A・B〈数列・ベクトル〉)のうちから1科目選択 | 100 |
| 総合計 | 450 | |
社会安全学部
| 教科 | 科目 | 配点 |
| 外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
| 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(いずれも漢文を除く) | 150 |
| 地歴・公民または数学 | 世界史B、日本史B、地理B、政治・経済、数学(数学Ⅰ・Ⅱ、数学A・B〈数列・ベクトル〉)のうちから1科目選択 | 100 |
| 総合計 | 450 | |
化学生命工学部
化学生命工学部は入試方法が3つあるので、以下をチェックしておきましょう。
〈理科1科目選択方式〉
| 教科 | 科目 | 配点 |
| 外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
| 数学 | 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、数学A・B(数列・ベクトル) | 200 |
| 理科 | 物理(物理基礎・物理)、化学(化学基礎・化学)、生物(生物基礎・生物)のうちから1科目選択 | 150 |
| 総合計 | 550 | |
〈理科設問選択方式(2科目型)〉
| 教科 | 科目 | 配点 |
| 外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 150 |
| 数学 | 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、数学A・B(数列・ベクトル) | 200 |
| 理科 | 物理(物理基礎・物理)、化学(化学基礎・化学)、生物(生物基礎・生物)のうちから2科目を学科により指定。指定された2科目のそれぞれ3問ずつの合計6問のうち、試験時間中に4問を選択 | 200 |
| 総合計 | 550 | |
〈理科設問選択方式〉
| 教科 | 科目 | 配点 |
| 外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 150 |
| 数学 | 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、数学A・B(数列・ベクトル) | 200 |
| 理科 | 物理(物理基礎・物理)、化学(化学基礎・化学)のそれぞれ3問ずつの合計6問のうち、試験時間中に3問を選択 | 200 |
| 総合計 | 550 | |
出願者数や合格者数のデータ
関西大学の志願者数や合格者数は以下のとおりです。なお、ここで取り上げるのは2022年度(令和4年度)一般入試の結果です。
| 学部 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
| 法 | 6,540 | 1,717 | 3.7 |
| 文 | 7,192 | 1,571 | 4.5 |
| 経済 | 5,777 | 1,306 | 4.4 |
| 商 | 6,058 | 1,366 | 4.4 |
| 社会 | 5,339 | 1,407 | 3.8 |
| 政策創造 | 3,406 | 581 | 5.8 |
| 外国語 | 1,998 | 478 | 4.1 |
| 人間健康 | 3,072 | 519 | 5.8 |
| 総合情報 | 3,615 | 736 | 4.8 |
| 社会安全 | 2,491 | 441 | 5.5 |
| システム理工 | 5,674 | 1,851 | 3.0 |
| 環境都市工 | 3,107 | 1,075 | 2.8 |
| 化学生命工 | 3,177 | 1,360 | 2.3 |
関西大学に合格するための勉強方法

ここまで関西大学についていろいろと解説しましたが、受験生にとって1番知りたい情報は「どのように勉強したら合格できるのか」ではないでしょうか?ここでは、関西大学に入るには何をすればいいのか、受験期の過ごし方や勉強ポイントをご説明します。
後半には四谷学院がなぜ関西大学合格のためにおすすめなのかも解説しているので、ぜひチェックしてみてください。
関西大学に入るには、何をすればいい?
関西大学に合格するためには、基礎をしっかり学習しておくことが最も大切です。出題される問題は難問・奇問というものではないため、ライバルの受験生もある程度は解くことができるということです。そのため、どれだけミスなく解くことができるかが重視されます。
単語や文法、用語や熟語など、基本的な知識を「なんとなく」ではなく正確に頭に入れるよう、何度も繰り返し学習し、用語の背景と一緒に覚える工夫をするとよいでしょう。
受験期の過ごし方
高校3年生の受験期をどう過ごすのかによって、合否が分かれると言われています。最も重要なのはスケジュール管理なので、ここでは1年計画をご紹介します。以下を参考にして、自分の計画を立ててみましょう。
・春(4〜6月):全ての科目において、基礎を学習することに注力しましょう。教科書や易しめの問題集を繰り返しおこなうのが有効です。
・夏(7〜9月):これまでの学習の総復習をおこないましょう。特に夏休みは集中的に学習できる最後のチャンスなので、ここで苦手分野を克服しておくのがおすすめです。
・秋(10〜12月):ここまでインプットしてきた知識をアウトプットできるように訓練しましょう。入試レベルの問題集などを繰り返し解くのがおすすめです。
・冬(1〜3月):入試直前は、過去問演習をおこないましょう。実際の試験時間通りにおこなうことで時間配分の練習もできますし、本番の緊張を和らげることができます。
勉強のポイント
関西大学の試験科目ごとの勉強ポイントは、以下のとおりです。
・英語:英語の難易度は標準レベル。そこまで難しくないからこそ、1つのミスが大きく響きます。英単語や熟語、文法などの基礎をしっかりと固めるようにしましょう。
・国語:古文は基礎知識が問われるので、正確な知識を身に付けておくようにしましょう。・数学:難易度は標準的といわれています。記述式では相手に伝わる書き方をすることが重要なので、学校の先生や予備校の講師にチェックしてもらうのがおすすめです。
予備校で勉強する場合
予備校に通っているからといって、安心してはいけません。ただ授業を聞いているだけで得られることは、実は驚くほど少ないのです。関西大学に合格するために必要なのは、授業を受けて得た知識を実際に使えるようになること。
そのためには、予備校のテキストだけではなく、過去問や青チャートなどの市販されている問題集なども上手に組み合わせて学習するのがおすすめです。自分の苦手分野や頻出問題を中心に学習するのがベストなので、分からないようであれば予備校の講師に聞くようにしましょう。
予備校に通っているからと受け身でいるのではなく、能動的に学習するのが重要です。
予備校の注意点・落とし穴については以下の記事もぜひご覧ください。
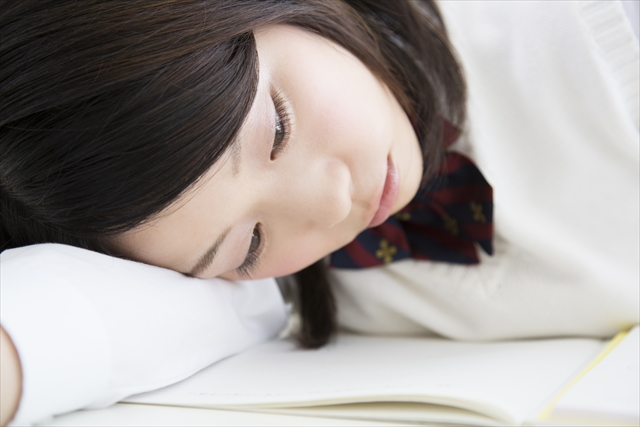
四谷学院のダブル教育システムのご案内
四谷学院は、数多くの関西大学合格者を輩出しています。その理由は、四谷学院ならではの「ダブル教育」システム。ダブル教育とは、科目別能力別授業と55段階個別指導の2つを合わせることにより、確実な知識の定着を図ることができる学習方法です。
それぞれの特徴やメリットを、以下で見ていきましょう。
科目別能力別授業
00人規模の集団授業を行っている予備校は多くあります。しかし、同じ授業を受けていても100人の学習レベルはさまざまなことがほとんど。自分のレベルに合っていない授業を受けていても、そもそも理解できなかったり効率良く学習できなかったりとデメリットが生じてしまいます。
そこで四谷学院では、科目別・能力別でクラス分けを実施し、自分のレベルにあった授業を受けられるシステムを構築。より効率の良い学習ができるようになっています。
55段階個別指導
自分のレベルに合った集団授業を受けていても、なかなか知識が定着しないこともあるでしょう。そこで有効なのが、55段階個別指導です。
実は、集団授業を受けていることで得られるのは、「知識のインプット」だけ。実践力を身に付けるためには「知識のアウトプット」がスムーズにできる練習を行う必要があるのです。55段階個別指導では、知識を落とし込んで実際に使う「理解と実践」という作業を行うので、知識の定着や応用ができるようになります。
まとめ
【関西大学の入試概要】
・多様性を尊重し、身に付けた知識を実践して困難を克服できる人材が求められています
・入試方法は豊富だが、「一般入試」「共通テスト利用入試」の2種類が一般的
・「関関同立」の一校で、学部によって異なるが、難易度はやや難~難。
【関西大学の入試データまとめ】
・2022年度一般入試の全学日程で、倍率は2.3〜5.8倍。
【勉強方法まとめ】
・基礎レベルの問題が多く出題されるので、教科書を中心とした基礎学力をしっかりと身に付けておくことが重要
・過去問を解いて、解く方法や時間配分などの練習をしておくのがおすすめ
関関同立の一つである関西大学は、全国的な名門大学。受験生も多く、難易度もやや難~難レベルと、厳しい戦いになりやすい大学でもあります。そんな関西大学に合格したい方は、ぜひ四谷学院への入学をご検討ください。四谷学院の「ダブル教育」により自分のレベルにあった授業を受けることで、効率的に教育効果を実感できます。四谷学院では個別相談会も行っているので、ぜひ一度お問い合わせください。
※本記事でご紹介した情報は2022年12月22日現在のものです。最新の情報は大学公式ホームページにて必ずご確認ください。